「SESはやめとけ」という情報を見て将来に不安を感じていませんか?
新卒や未経験でSESの世界に入ったものの、ブラック企業の噂や労働環境の悪さを耳にして、このままでいいのかと悩んでしまいますよね。
この記事を読めば、なぜ「SESやめとけ」と言われるのか、その本当の理由が明確になり、自信を持って次のキャリアを選択する指針が得られます。
SES業界の構造的な問題から、あなたの経験を武器に転職を成功させる具体的な戦略までを徹底解説します。
もう先の見えない不安に悩むのは終わりです。納得のいくキャリアを歩むための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
\ 転職者の約8割が年収アップに成功 /
高単価案件を今すぐチェック(無料)TOPICS
SESはやめとけ?その理由とよくある問題点
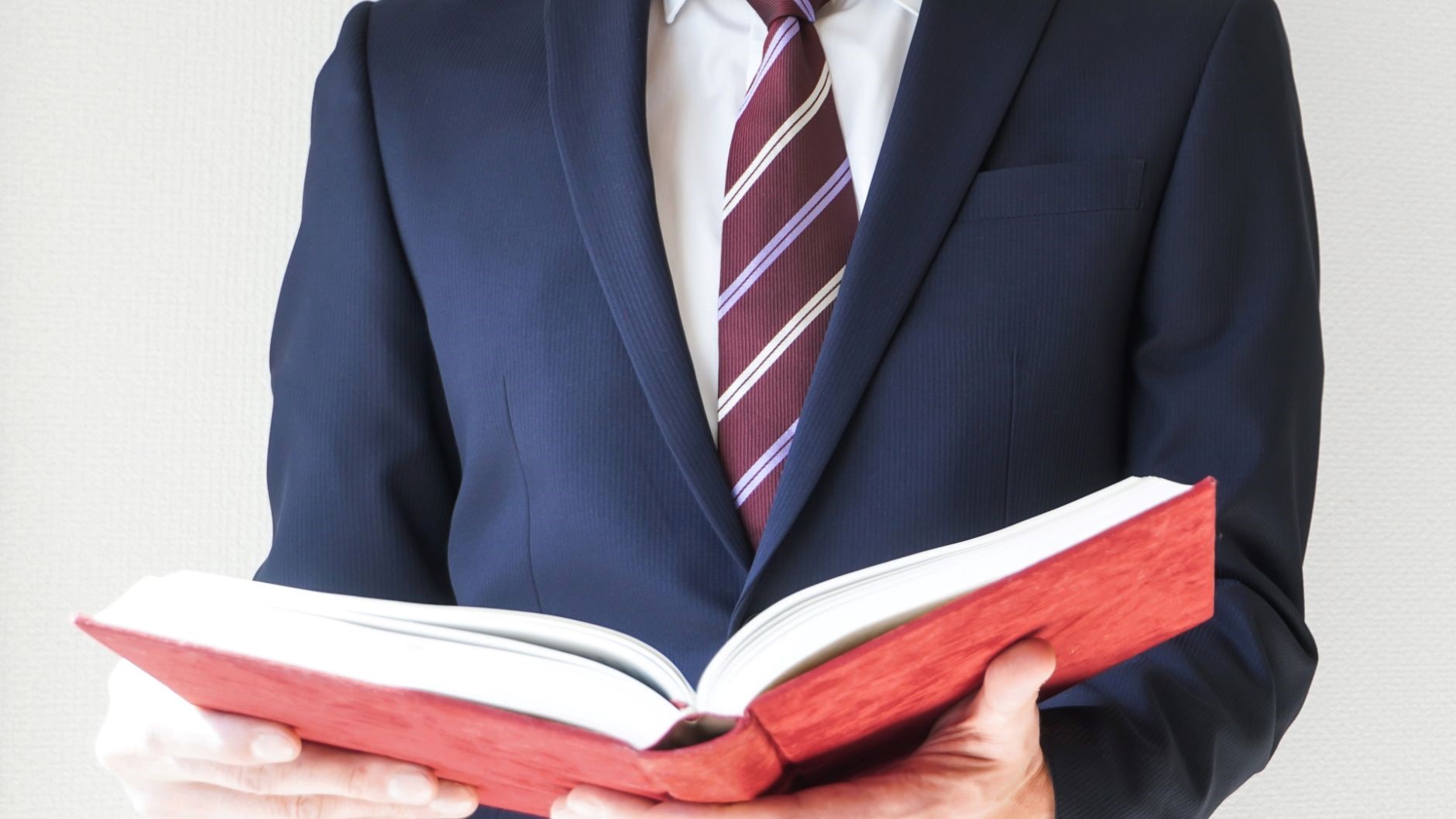
日々の業務で感じる将来への漠然とした不安は、実はSES業界特有の構造的な問題に根差しているのかもしれません。
この章では、「SESはやめとけ」と言われる背景にある構造的な問題について詳しく解説します。
SES企業で働く際の問題点には以下の内容があります。
- 多重請負構造による給与上昇の限界
- 案件選択の自由度が低く、スキルミスマッチが発生しやすい環境
- 客先常駐による所属感の希薄さと精神的負担
- 中間搾取による労働対価の減少
- 体系的なスキルアップ機会の不足
給料が上がりにくい構造
SES企業では多重請負構造と固定的な人件費モデルにより、個人の成長やスキル向上が給与に反映されにくい構造的な問題があります。SES企業の収益モデルは客先への人材派遣による固定単価制が中心で、エンジニア個人のスキル向上や成果が直接的な単価アップに繋がりにくいためです。
また、評価基準が稼働時間重視で、技術力や成果物の質よりも安定して現場に出続けることが評価される傾向があります。
例えば、3年間同じ案件で優秀な成果を上げ続けても、客先との契約単価が変わらない限り昇給は期待できません。実際に、SES企業では昇給ペースが緩やかで、5年間勤務しても昇給額が50万円程度に留まるケースも見られます。
厚生労働省の統計によればIT業界全体の賃金は経験と共に上昇するため、問題は昇給がないことではなく、その上昇率が低い点にあります。
特に、大手SIerや有力なWeb系企業に勤務する同世代のエンジニアと比較した場合、年収差が100万円から200万円、あるいはそれ以上に開くことも珍しくありません。
給与の伸び悩みを感じている場合は、現在の会社での昇給可能性を客観的に分析し、転職市場での自分の価値を調査することをおすすめします。
参考:厚生労働省 「賃金構造基本統計調査」
厚生労働省「IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業」
openwork「平均年収ランキング SIer、ソフト開発、システム運用」
案件ガチャによるミスマッチの多さ
SES業界では案件ガチャと呼ばれるように、自分の希望や適性に関係なく案件が決まることが多く、キャリア形成に大きな弊害をもたらします。
SES企業は利益確保のため、エンジニアの希望より客先の要求や空いている案件を優先する傾向です。また、営業担当者の技術的な理解不足により、エンジニアのスキルと案件要求のミスマッチを起こしやすい構造です。
具体的には、以下のようなケースが頻発しています。
- Javaを学びたい新卒エンジニアが、人手不足のCOBOLの保守案件に配属され、3年間古い技術しか触れられないケース
- フロントエンド志望者がインフラ案件に回されて全く異なるキャリアを歩むことになるケース
このような案件選択の自由度が低い環境では、自分でキャリアをコントロールできません。
希望する技術領域が明確な場合は、その分野に特化した企業への転職を検討すべきです。
客先常駐の孤独感とストレス
客先常駐では所属感の欠如や頻繁な環境変化により、精神的な負担が大きく、メンタルヘルスに深刻な影響を与えるかもしれません。
常駐先では外部の人として扱われることが多く、重要な意思決定から除外されることや、チームの一員として認められないことが頻繁にあります。また、案件が終わるたびに人間関係をゼロから作り直す必要があり、常に緊張状態を強いられるでしょう。
例えば、飲み会や懇親会に誘われなかったり、プロジェクトの根幹に関わる相談をされなかったりと、様々な場面で疎外感を覚えてしまうのです。
さらに、3ヶ月から6ヶ月ごとに職場が変わることで、深い人間関係を築けず、相談相手がいない孤独感に悩むエンジニアが多数います。
安定した人間関係と所属感を重視する方は、客先常駐が中心のSES企業よりも、自社開発や社内SEのポジションを検討することをおすすめします。
多重下請け構造がもたらす弊害
IT業界の多重下請け構造は、SESエンジニアが自身の働きに見合った適正な報酬を得られなくする、深刻な問題を引き起こしています。
大手SIerから下請け、孫請けへと案件が流れていく過程で、各企業がマージンを抜いていくため、実際に開発を担当するエンジニアに渡る金額は大幅に減ってしまいます。この構造は責任の所在も曖昧にするため、エンジニアが不当な扱いを受けても状況が改善されにくいのです。
例えば、クライアントが月額100万円で発注した案件であっても、三次請けのエンジニアには月50万円から60万円程度しか支払われない、といったケースもみられます。
さらに、プロジェクトでトラブルが発生した際の責任や、無理な納期設定のしわ寄せは、構造の末端にいるエンジニアに押し付けられてしまいます。
自身の労働対価を正当に評価されたいと強く願うのであれば、多重下請けに依存しない自社開発企業や、クライアントと直接契約する案件を多く扱う企業へ転職することが、最も現実的な解決策と言えるでしょう。
スキルアップの機会が少ない現実
SES企業では、会社として体系的な研修制度や新技術への投資に消極的な場合が多く、個人のスキルアップの機会が少ない環境です。SES企業は人材を客先に派遣することで利益を得るため、エンジニアの技術研修に十分な投資をするインセンティブが低く、即戦力として稼働できることが優先されます。
その結果、客先のプロジェクトで使う技術は固定化され、新しいスキルに触れる機会も自然と限られてしまうのです。
多くのSES企業では新人研修が数週間程度で終了し、その後は現場でのOJTに依存します。
しかし、常駐先では教育コストを嫌がられるため、十分な指導を受けられずにスキルが身につかないまま年数だけが経過するケースが多数あります。
また、最新のクラウド技術やフレームワークを学ぶ機会がなく、市場価値の低い古い技術のみに特化してしまうことは問題です。
技術的成長を重視する場合は、充実した研修制度と最新技術に触れる機会がある自社開発企業への転職、または個人での学習投資を積極的に行い、転職に向けたスキルアップを図ることが重要です。
SESで働くメリット
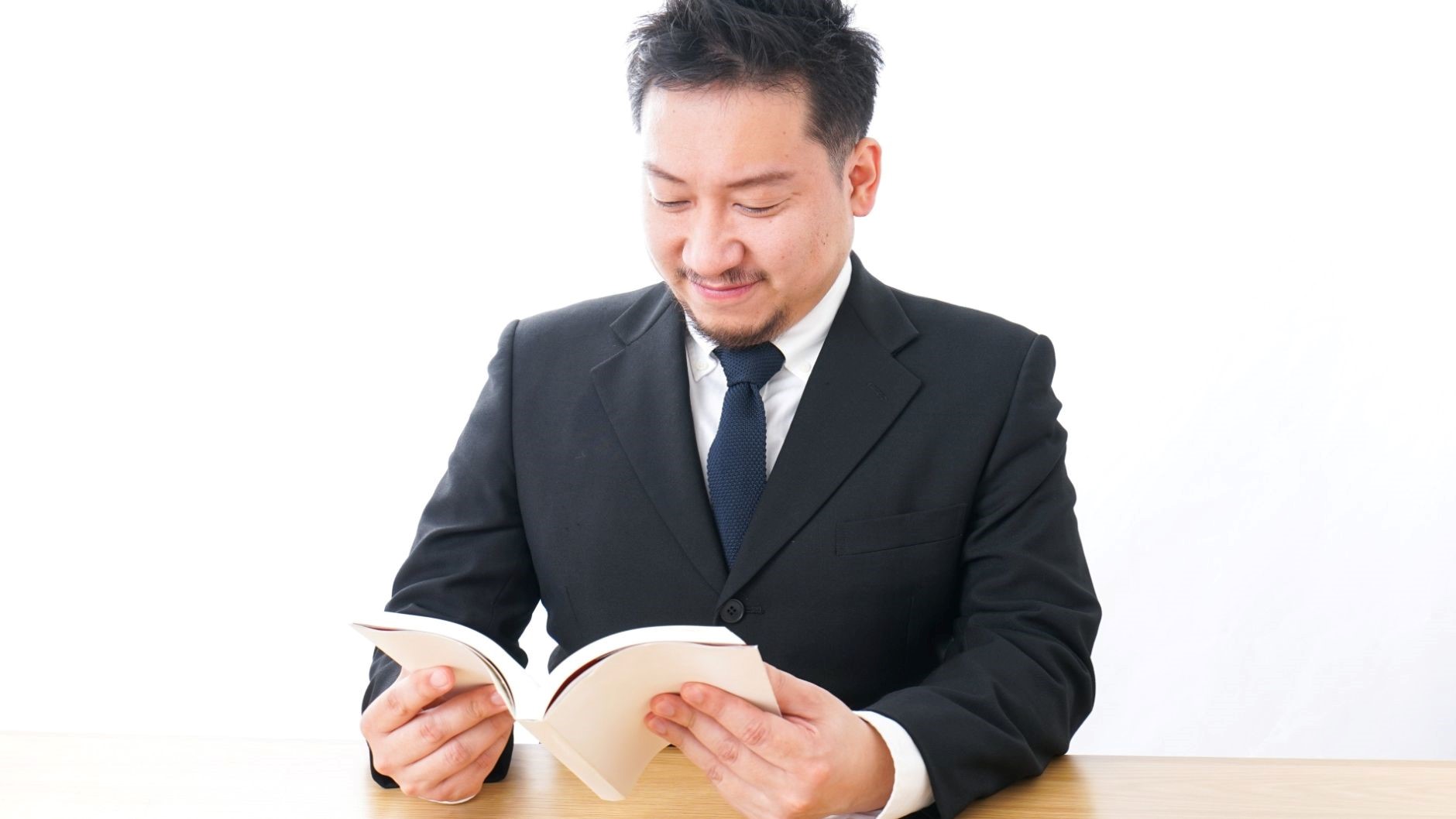
SESには構造的な問題点が指摘される一方で、キャリア形成の初期段階においては、戦略的に活用できるメリットも存在します。
この章では、SESで働くことがもたらす具体的なメリットについて、以下の観点から解説します。
- 未経験者でも実際のシステム開発に携わる実務経験の獲得機会
- 複数の業界や技術に触れることで得られる幅広い経験とスキル
- キャリアチェンジを目指す人にとって門戸が広い採用環境
未経験でも実務経験を積める
SES企業は、未経験からでも実際のシステム開発プロジェクトに参加できる、貴重な機会を提供してくれます。
これは、転職市場で非常に重視される「実務経験」を短期間で獲得できる、大きなメリットです。
多くの自社開発企業や大手IT企業では即戦力を求めるため、未経験者の採用は限定的です。
一方、SES企業は人材育成と派遣をビジネスモデルとしているため、未経験者を積極的に採用し、現場での実務を通じて育成する体制が整っています。
プログラミングスクール卒業後にSES企業に入社した未経験者が、3ヶ月の研修を経て金融系のWebアプリケーション開発案件に参画し、1年後には要件定義から設計、実装、テストまでの一連の開発工程を経験できるケースが多数あります。
このような実務経験は、転職活動において実際の「開発経験あり」として高く評価されるでしょう。
未経験からIT業界に入る場合、SESでの実務経験は転職市場での大きなアドバンテージとなるため、経験を積みながら次のキャリアステップを計画することが重要です。
多様な業務経験を得られる
SESの客先常駐という働き方を通じて、異なる業界の知識、様々な技術スタック、そして多様な開発手法に触れることが可能です。
その結果、エンジニアとして幅広いスキルセットと高い適応力を身につけられるでしょう。
自社開発企業では特定の技術や業務領域に特化する傾向がありますが、SESでは案件ごとに異なる環境で働くため、多様な技術や業務に触れる機会が豊富です。
様々な企業文化や開発体制を経験することで、コミュニケーション能力や問題解決能力が自然と向上し、これらのスキルは転職市場において環境適応力やマルチスキル人材として評価されます。
例えば、SESエンジニアは2年間で製造業のERPシステム開発、ECサイトのフロントエンド開発、金融機関のインフラ構築案件を経験し、Java、React、AWSといった異なる技術スタックを習得できます。
また、アジャイル開発とウォーターフォール開発の両方を経験すれば、プロジェクト管理手法の理解も深められるでしょう。
多様な経験は転職活動でどんな環境でも活躍できる人材として強いアピールポイントになるため、各案件での学びを整理し、スキルマップとして可視化することが重要です。
未経験歓迎の求人が多い
SES業界の大きな特徴として、未経験者を歓迎する求人が非常に多い点が挙げられます。これは、他業種からIT業界へのキャリアチェンジを考える人にとって、最も現実的な入口と言えるでしょう。
IT業界全体の慢性的な人材不足を背景に、特にSES企業は常に人材を確保する必要があります。
人を客先に派遣することが収益の源泉であるため、即戦力だけでなく、将来性を見込んだポテンシャル採用にも積極的なのです。
このため、エンジニア経験の有無はもちろん、文系出身であることや前職の内容が問われにくく、採用の門戸が広く開かれています。
年齢のハードルも比較的低く、30代からIT業界に挑戦する人も少なくありません。実際に、営業職や事務職など、全く異なる分野からキャリアチェンジを果たし、ITエンジニアとしての道を歩み始めている例は数多く報告されています。
このように求人の選択肢が豊富であることは、IT業界への第一歩を踏み出す上で大きな安心材料になります。
この「採用されやすさ」を戦略的に活用し、キャリアのスタート地点としてSESを選択することは、非常に有効な手段の一つです。
SESで働くデメリット

メリットを活かしてキャリアを築く道がある一方で、目を逸らすことのできないデメリットやリスクが存在するのも事実です。
この章では、SESで働くことの具体的なデメリットについて紹介します。
SESで働く際の問題点には以下の内容があります。
- スキルレベルを偽って案件に参画させられる経歴詐称の強要リスク
- 開発業務以外の雑務や事務作業に従事させられるケースの多さ
- 業界全体の高い離職率が個人のキャリアに与える悪影響
- 多重下請け構造による低い還元率と収入アップの困難さ
経歴詐称を強要されるリスク
一部のSES企業では、受注確率を上げるためにエンジニアのスキルや経験を偽って客先に提示することがあります。
これは配属後のスキルミスマッチや過大な精神的負担につながりかねない、非常に深刻な問題です。
案件獲得競争の中で、エンジニアのスキルシートに実際の経験年数より長い期間を記載したり、触ったことのない技術を「経験あり」としたりするケースが後を絶ちません。
特に営業担当者の技術理解が不足していると、無理な条件で案件を受注してしまい、結果としてエンジニアが現場で対応できず、孤立無援の状態に追い込まれてしまうのです。
例えば、Java経験1年の新人エンジニアが「3年の開発経験あり」として大規模システムのリーダー役で配属され、業務についていけずに精神的に追い詰められてしまうこともあるようです。
また、フロントエンドの経験しかないのにインフラ構築の経験者として現場に入り、全く役に立たず、契約が早期終了となる例も報告されています。
経歴詐称を強要するような企業は断固として避け、自身のスキルレベルを正直に評価してくれる優良SES企業を選ぶか、スキルに見合った自社開発企業への転職を検討することが、自分自身を守る上で極めて重要です。
エンジニア以外の業務を任されるケース
SESでは、エンジニアとして雇用されたにもかかわらず、開発とは無関係な事務作業や雑務を任されることが多くあります。これは技術的な成長を大きく阻害する要因になり得ます。
客先の部署で人手が足りない場合、SESエンジニアが便利な労働力として、様々な業務に回されてしまうことがあるのです。
契約内容が「システム関連業務全般」のように曖昧だと、データ入力、書類整理、電話対応といった非技術的な業務を押し付けられやすい構造的な問題も潜んでいます。
実際に、システム開発案件として配属されたエンジニアが、顧客データのExcel入力や電話サポート、議事録作成ばかりに従事させられ、半年間全くプログラミングに触れられなかったという話も聞かれます。
テスト業務として入ったものの、実際は手動でのデータチェック作業の繰り返しで、自動化スキルが全く身につかないという状況も少なくありません。
契約を結ぶ前に具体的な業務内容を詳細に確認し、もし技術的成長に繋がらないと感じた場合は、その案件を断る権利を行使すべきでしょう。
それが難しい場合は、明確な開発業務に従事できる環境への転職を真剣に考える必要があります。
離職率の高さとその影響
一部のSES企業では離職率が非常に高く、それが組織の不安定さや人間関係の希薄さに繋がり、個人のキャリア形成やメンタルヘルスに悪影響を及ぼすかもしれません。
給与の低さ、キャリアパスの不明確さ、客先常駐による孤独感といった要因が複合的に作用し、他業界の平均を大きく上回る離職率を示す企業も存在します。
離職率が高いと、継続的な人間関係の構築が困難になります。これでは先輩から十分な指導を受けたり、気軽に相談したりすることが難しくなり、特に新人エンジニアの成長が妨げられてしまうでしょう。
例えば、入社1年目のエンジニアが頼りにしていた先輩たちが半年で全員転職してしまい、技術的な相談相手を失って成長が止まってしまいます。あるいは、チームメンバーの入れ替わりが激しすぎて、プロジェクトの品質維持が困難になることも頻繁に起こり得ます。
こうした人材の流出は、社内に技術やノウハウが蓄積されないという結果を招き、組織全体のスキルレベルが向上しない悪循環を生み出してしまうのです。
もしあなたが安定した企業環境で長期的なキャリアを築きたいのであれば、離職率の低い自社開発企業や、定着率の高いSIerへの転職を積極的に検討することをおすすめします。
還元率が低く収入が上がりにくい
SESの給与体系における最大の問題点は、エンジニア個人の働きが正当に収入へ反映されにくい構造にあることです。
これには「還元率の低さ」と「収入の上がりにくさ」という2つの側面が関わっています。
まず「還元率」とは、客先から支払われるエンジニアの単価のうち、実際にエンジニアの給与として支払われる割合のことです。
業界の構造上、この還元率が低く抑えられがちで、例えば月額単価100万円の案件であっても、エンジニアの給与は50万円から60万円程度というケースも少なくありません。
さらに深刻なのが「収入の上がりにくさ」です。
SES企業の多くは、客先と固定単価で契約を結んでいます。
そのため、たとえあなたが現場でスキルを磨き、高い成果を上げて客先から評価されたとしても、それが契約単価の見直しに繋がらない限り、あなたの給与に反映されることはほとんどありません。
結果として、3年間同じ案件で優秀な成果を出し続けても、大幅な昇給は期待できず、同世代の自社開発エンジニアとの年収差が100万円から200万円に開いてしまう、といった事態が起こり得るのです。
自身のスキルや成果に見合った適正な対価を得たいと考えるならば、この収入構造の問題を理解し、より還元率の高い企業や、個人の成果を直接評価してくれる自社開発企業への転職を視野に入れることが、現実的な解決策となるでしょう。
SESで成功する人の特徴
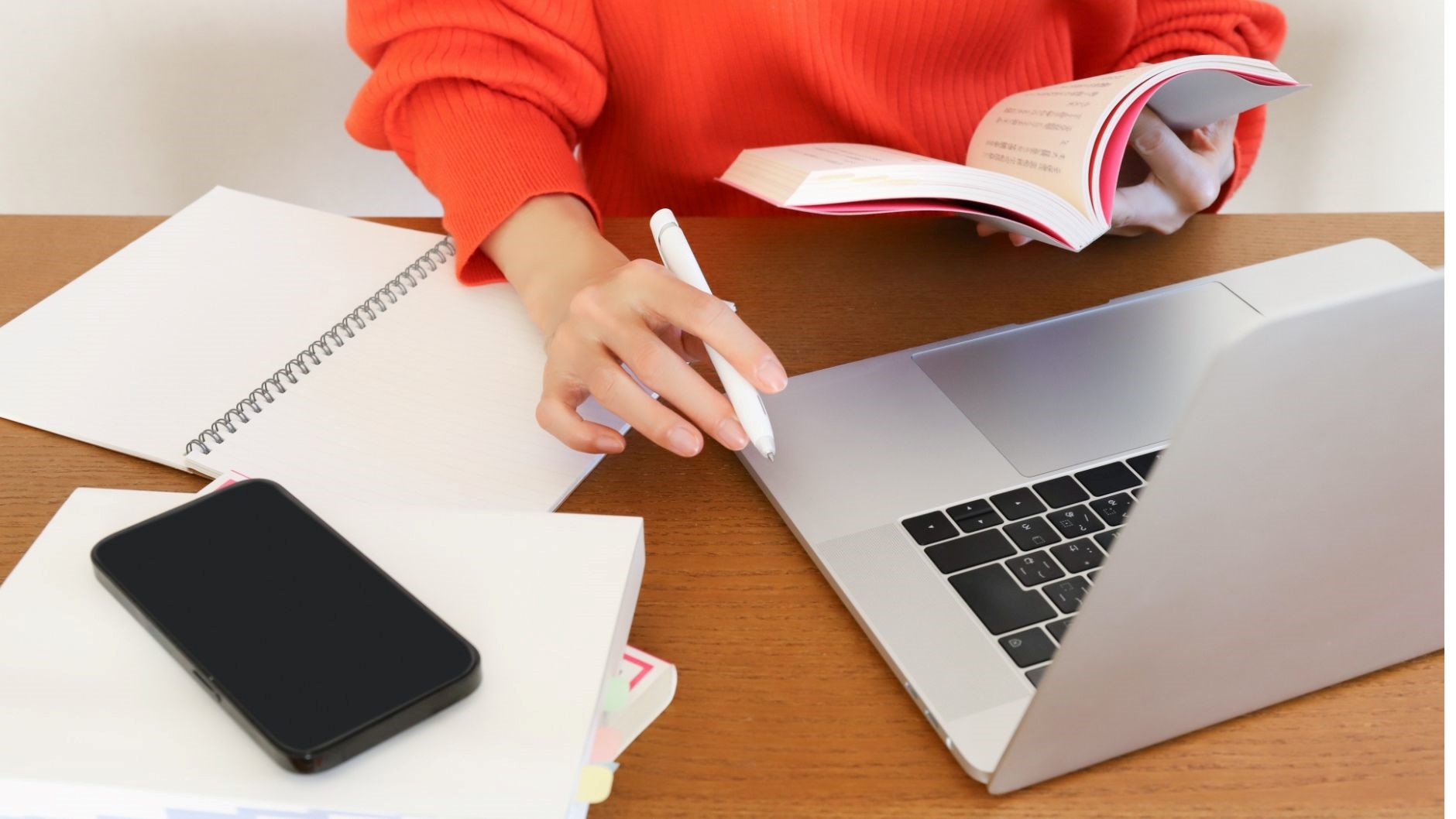
厳しい側面がある一方で、SESという環境を戦略的に活用し、キャリアアップを成功させているエンジニアも確かに存在します。
この章では、SESで成功する人の具体的な特徴について紹介します。
成功を収めるエンジニアには、主に以下のような共通点が見られます。
- 環境変化を成長機会として活用できる高い適応力と学習への積極性
- 客先常駐で様々な人と協働するための優れたコミュニケーション能力
- SESを踏み台とした将来への明確なキャリアプランと戦略的思考
- 業務外でも継続的に市場価値向上を図る自主的なスキルアップ能力
高い適応力と積極的な学習意欲
SESで成功する人は、頻繁な環境変化をストレスではなく、多様な経験を積める貴重な機会として前向きに捉えています。そして、継続的な学習を通じて自身の市場価値を高めていくのが特徴です。
SESでは案件ごとに業界、技術スタック、開発手法が変わるため、変化を嫌う人には厳しいかもしれません。
しかし、適応力の高い人にとっては、短期間で多様な経験を積める理想的な環境と言えるでしょう。
新しい技術や業務に対して積極的に学習する姿勢があれば、各案件で得られる知識とスキルを効率的に蓄積でき、転職市場での競争力を大幅に向上させることができます。
実際に、製造業のERPシステム開発、ECサイトのフロントエンド開発、金融機関のインフラ構築と異なる案件を渡り歩き、各現場で新しい技術を意欲的に学習したエンジニアがいました。
その結果、Java、React、AWSといった幅広いスキルセットを習得し、3年後には大手自社開発企業への転職を成功させています。
変化を恐れず、むしろ成長の機会として捉える考え方を持ち、常に新しいことを学ぶ意欲を維持することで、SESでの経験を最大限に活用できます。
優れたコミュニケーション能力を持つ
SESで成功する人は、客先常駐という環境を活かし、様々な立場の人と巧みに関係を構築します。それによってプロジェクトを円滑に進め、自身の評価を着実に高めていくのです。
客先常駐では短期間で新しいチームに溶け込み、クライアントや同僚との信頼関係を築く必要があります。
優れたコミュニケーション能力を持つ人は、要件のヒアリング、進捗報告、課題の相談といった業務を円滑に進めることができ、また一緒に働きたいと評価されることで継続的に良い案件を獲得しやすくなるでしょう。
また、この能力は転職活動でも高く評価される重要なスキルです。
技術力だけでなく、人との関わりを大切にし、積極的にコミュニケーションを図れば、SESでの経験をキャリアアップにつなげられます。
明確なキャリアプランがある
SESで成功する人は、明確なキャリアプランを描き、将来の目標から逆算して戦略的に案件を選択します。そして、SESでの経験を計画的に自身のキャリアを形成していくために活用しているのです。
明確なキャリアプランがあれば、単に割り当てられた案件をこなすのではなく、将来の自分に必要なスキルや経験は何かを意識して、主体的に案件を選択できるようになるでしょう。
また、転職のタイミングや必要な準備についても計画的に進められるため、SESから希望する企業への転職成功率も大幅に向上させられます。
Web系自社開発企業への転職を目標に定め、2年間でフロントエンド、バックエンド、インフラの案件を戦略的に経験したエンジニアの場合、業務外でポートフォリオを作成しながら転職活動を行い、見事に希望していた企業のフルスタックエンジニアとして採用された、という事例があります。
5年後、10年後の自分がどうなりたいかを明確にし、そこから逆算してSESでの経験を積むことで、確実にキャリアアップを実現できます。
漫然と業務をこなすのではなく、戦略的思考を持って行動することが成功につながります。
自主的にスキルアップできる人
SESで成功する人は、業務時間外でも継続的に学習を行い、市場価値の向上を意識した自己投資を積極的に行っています。
SES企業では体系的な研修制度が不足していることが多いため、自分でスキルアップしているのです。
自主的に学習を継続できる人は、業務で得られない最新技術の習得、資格取得、ポートフォリオ作成などを通じて市場価値を高め、より良い案件獲得や転職成功に繋がっていきます。
実際に、業務ではレガシーなシステムの保守作業が中心だったエンジニアが、業務外でモダンなフレームワークを学習し、個人プロジェクトでWebアプリケーションを開発してGitHubで公開しました。そのポートフォリオが評価され、希望していたスタートアップ企業への転職を成功させたというケースも報告されています。
業務だけに依存するのではなく、自分の市場価値を高めるために継続的な学習投資を行うことが、SESでの経験を活かし転職成功につながります。
自己研鑽を怠らず、常に成長し続ける姿勢が何よりも重要になるのです。
優良SES企業の見極め方
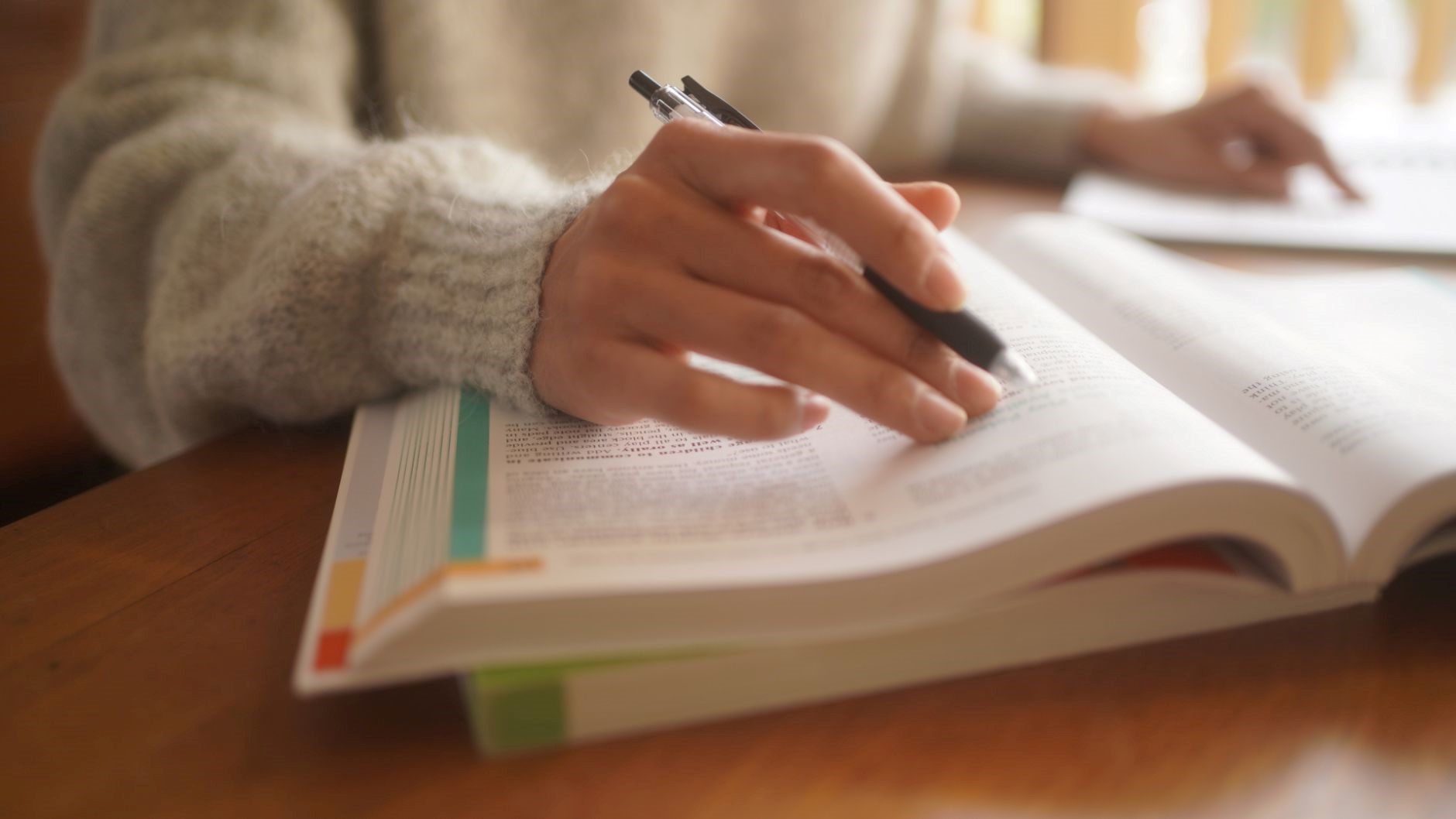
すべてのSES企業が同じ問題を抱えているわけではなく、中にはエンジニアの成長を真摯に支援する「優良企業」も存在します。
この章では、優良SES企業の見極め方について紹介します。
後悔しない企業選びをするために、特に注目すべきポイントは以下の通りです。
- 技術力向上とキャリア形成に繋がる自社開発サービスの有無
- エンジニアの希望を尊重した多様な業務内容と派遣先の選択肢
- 公正で透明性の高い評価制度による昇進・昇格の明確化
- 継続的なスキルアップを支援する充実した研修・教育体制
- 案件間の待機期間における安定した給与保証制度
自社開発サービスがあるか
優良なSES企業は、自社でサービスを開発・運営していることがあります。
これは、エンジニアが客先常駐だけでなく、自社プロダクト開発にも携われる環境があるという大きなメリットです。
自社開発サービスを持つ企業は、単なる人材派遣にとどまらず、技術力の向上に投資する意欲があります。それは、エンジニアのスキルアップと市場価値向上を真剣に考えている証拠といえるでしょう。
また、自社サービスの開発経験は、転職活動の際に「プロダクト開発経験」として高く評価され、将来的に自社開発企業へ移る際に有利に働く可能性が高いのです。
例えば、自社でWebサービスやモバイルアプリを運営している企業では、エンジニアが客先常駐と自社開発を交互に経験し、幅広いスキルセットを効率的に身につけることができます。
実際に、自社のECサイト開発を経験したSESエンジニアが、その実績を武器に大手EC企業への転職を成功させたという事例も報告されています。
さらに、自社サービスは収益の柱を多様化させるため、企業として安定した経営基盤を築いていることが多い点も魅力です。
求人情報や企業HPで自社サービスの有無を必ず確認し、面接では自社開発に携わる機会について具体的に質問することをおすすめします。
業務内容や派遣先の選択肢が多いか
優良なSES企業は、多様な業界や技術領域の案件を豊富に保有しており、エンジニア一人ひとりの希望やキャリアプランに応じて案件を選択できる環境が整っています。
案件の選択肢が多いということは、その企業の営業力が強く、クライアントと良好な関係を築けているということです。そのため、安定した案件供給も期待できるでしょう。
また、エンジニアの希望を尊重する姿勢は、離職率を下げ、長期的な人材育成に取り組んでいる証拠です。
多様な案件経験により、転職市場で求められる幅広いスキルセットを効率的に身につけられます。
例えば、金融、製造、Web、インフラといった幅広い業界の案件を扱い、Java、Python、React、AWSなど多様な技術スタックを選択できる企業であれば、自分のキャリアプランに沿って戦略的に経験を積んでいくことが可能です。
フロントエンド志向やインフラ特化など、個々の希望に応じた案件マッチングに力を入れている企業も存在します。
面接時に具体的な案件例を聞き、自分の希望する技術領域の案件があるか、案件選択にエンジニアの意見が反映されるかを確認しましょう。
評価制度の透明性が高いか
優良SES企業は明確な評価基準と昇進・昇格の仕組みを公開し、エンジニアが納得感を持ってキャリア形成できる透明性の高い評価制度を導入しています。
透明性の高い評価制度があることで、エンジニアは自分の成長目標を明確に設定でき、モチベーション向上と計画的なスキルアップが可能になります。
また、評価基準が不明瞭な企業では昇給や昇進が営業担当者の裁量に左右されることが多く、公正な評価が期待できません。明確な制度がある企業は長期的な人材育成を重視している証拠でもあります。
技術スキル、プロジェクト貢献度、コミュニケーション能力などの評価項目を数値化し、半年ごとの評価面談で具体的なフィードバックを行う企業や、資格取得や技術ブログ執筆などの自己研鑽活動も評価に反映する制度を持つ企業が優良SES企業の特徴です。
面接で評価制度について詳しく質問し、評価基準や昇進の条件が明文化されているか、定期的な評価面談があるかを確認することが重要です。
充実した研修や教育体制があるか
優良SES企業は継続的なスキルアップを支援する体系的な研修制度と教育体制を整備し、エンジニアの市場価値向上に積極的に投資しています。
充実した研修体制がある企業は、エンジニアの長期的な成長を重視し、単なる人材派遣ではなく技術者育成に本気で取り組んでいます。
新人研修だけでなく、中堅エンジニア向けの技術研修、マネジメント研修、資格取得支援などがあることで、継続的なキャリアアップが可能です。
例えば、3ヶ月間の手厚い新人研修に加え、年2回の技術研修、外部セミナー参加費の補助、資格取得一時金制度、社内勉強会の定期開催といった制度を設けている企業も珍しくありません。
AWS認定資格やOracle認定資格の取得を奨励し、合格者に手当を支給する企業も存在します。
企業HPで研修制度を確認し、面接では具体的な研修内容、資格取得支援、継続教育の仕組みについて詳しく質問することをおすすめします。
待機期間中の給与保証があるか
優良SES企業は案件間の待機期間中も安定した給与を保証し、エンジニアが経済的不安なく次の案件に備えられる制度を整備しています。
待機期間中の給与保証がある企業は、エンジニアの生活安定を第一に考え、長期的な雇用関係を前提とした経営を行っていることの証明です。
給与が保証されることで、待機期間中にスキルアップへ集中したり、より良い案件を獲得するための準備に時間を使ったりすることが可能になります。
また、経済的な不安がないため、「とりあえず」で希望しない案件を受けざるを得ないといった状況も避けられるでしょう。
待機期間中も基本給の80パーセントから100パーセントを保証し、その期間中に社内研修や資格取得に専念できる制度を持つ企業や、最大3ヶ月間の待機期間保証と次案件決定までの転職支援を提供する企業があります。
また、待機期間をスキルアップ期間として位置づけ、積極的に学習機会を提供する企業も存在します。
契約条件として待機期間の給与保証について必ず確認し、保証期間や支給割合、待機期間中のサポート内容を明確にしておくことが重要です。
\転職後の就業継続率97%の転職支援/
希望条件に合う案件を無料で紹介SESからのおすすめキャリアパス

SESでの経験は決して無駄ではなく、その経験を活かして多様なキャリアパスを描くことが可能です。
この章では、SESからのおすすめキャリアパスについて紹介します。
具体的には、主に以下の3つの道筋が考えられます。
- 安定した企業環境で働ける社内SEへの転職による職場環境の改善
- 最新技術とプロダクト開発経験が積めるWeb系企業への転職
- 上流工程経験と高収入が期待できる大手SIerへのステップアップ
社内SEへの転職
社内SEは安定した労働環境と給与体系で働けるため、SESエンジニアにとって最も現実的で成功しやすいキャリアパスの一つです。
社内SEはユーザー企業の情報システム部門で働くため、客先常駐がなく安定した職場環境が得られます。SESで培った多様な業界・技術経験は社内SEの業務で高く評価され、システムの企画から運用まで幅広い知識が求められる社内SEにとって大きなアドバンテージとなります。
給与面でも一般企業の正社員として安定しており、残業も比較的少ない傾向です。
実際に、SESで金融系と製造業の案件を経験したエンジニアが、製造業企業の社内SEに転職し、業務システムの刷新プロジェクトでリーダーを務め、年収を100万円アップさせたという事例も報告されています。
また、インフラとアプリケーション両方の経験を持つSESエンジニアが、中堅企業の社内SEとして採用され、システム全体の最適化を任されて高い評価を得るケースも見られます。
SESでの多様な経験を幅広い知識とトラブル対応能力としてアピールし、希望する業界での実務経験を強調することで社内SEへの転職成功率を高めることができます。
Web系企業へのキャリアチェンジ
Web系企業への転職は技術的成長と高収入を実現できる魅力的なキャリアパスですが、事前のスキル準備と戦略的な転職活動が欠かせません。
Web系企業は最新技術を積極的に採用し、エンジニアの技術的成長を重視する文化があるため、スキルアップ志向の強いSESエンジニアには理想的な環境です。
成果主義の給与体系により、スキルと経験に応じて大幅な年収アップが期待できます。
一方で、モダンな技術スタックや自社サービス開発の経験が求められるため、SESでの経験だけでは不十分な場合があります。
例えば、SESでJavaの業務経験を積んだエンジニアが、業務外でReactとNode.jsを学習しました。
そして、個人プロジェクトでWebアプリケーションを開発してポートフォリオとして提示した結果、スタートアップ企業のフルスタックエンジニアとして転職を成功させ、年収を150万円アップさせたというケースがあります。
Web系企業への転職を目指す場合は、モダンな技術スタックの習得と個人プロジェクトによるポートフォリオ作成を並行して進め、SESでの経験を多様な環境での適応力としてアピールすることが重要です。
SIerへのステップアップ
大手SIerへの転職は上流工程の経験と高収入を実現できる安定したキャリアパスであり、SESでの実務経験が直接的に評価される転職先として適しています。
SIerはSESエンジニアの実務経験と技術力を正当に評価する傾向があり、特に要件定義や設計といった上流工程にシフトしたいエンジニアにとって理想的な環境です。
大手SIerは安定した経営基盤と充実した福利厚生を持ち、長期的なキャリア形成が可能です。
SESで培った顧客折衝能力やプロジェクト経験は、SIerでのコンサルタント業務やプロジェクトマネジメントに直結するスキルとして高く評価されます。
SESで3年間の開発経験を積み、基本情報技術者とAWS認定資格を取得したエンジニアが、大手SIerのシステムエンジニアとして転職し、1年後には要件定義を担当するポジションに昇格して年収を200万円アップさせた事例があります。
SIerへの転職を成功させるためには、技術力の証明となる資格取得と、SESでの多様なプロジェクト経験を課題解決能力や顧客対応力として体系的にアピールすることが効果的です。
転職活動を成功させるエージェント活用術

希望のキャリアパスが見えてきても、あなたの経験価値を正しく理解し、強力に後押ししてくれるパートナーの存在は欠かせません。
この章では、転職活動を成功させるエージェント活用術について紹介します。
転職エージェントを最大限に活用し、成功を掴むためのポイントは以下のとおりです。
- SES経験を理解し適切にサポートできるエージェント選びの重要ポイント
- 転職成功率を高める効果的な面談準備と継続的な関係構築方法
- 好条件の非公開求人にアクセスするための戦略的なアプローチ
エージェント選びのポイント
SESからの転職を成功させるには、IT業界に精通し、SESでの経験価値を適切に評価できる専門性の高いエージェントを選ぶことが重要です。
一般的な転職エージェントでは、SES業界の特殊性やエンジニアのスキルを正しく理解できず、適切な求人紹介や面接対策は期待しにくいでしょう。
その点、IT特化型のエージェントであれば、SESでの多様な案件経験や客先常駐で培ったコミュニケーション能力を、転職市場で価値あるスキルとして正当に評価し、効果的なアピール方法を提案してくれるはずです。
特に、SES出身者の転職支援実績が豊富なエージェントを選ぶことが、成功の確率を大きく左右します。
実際に、IT特化エージェントを利用したSESエンジニアが、一般のエージェントでは評価されなかった客先常駐での経験を「環境適応力の高さ」としてアピールし、希望の自社開発企業への転職を成功させた事例も報告されています。
まずは複数のIT特化エージェントと面談し、担当者が自身の経歴や希望をどれだけ深く理解してくれるか、また過去の実績はどうかといった点を確認した上で、最も信頼できるパートナーを選びましょう。
効果的な面談準備と活用方法
エージェントとの面談を有効に活用するには、SESでの経験を体系的に整理し、転職の希望条件を明確に伝えることが、転職を成功させる上で非常に重要です。
なぜなら、転職エージェントは候補者の経験やスキルを正確に把握して初めて、最適な求人を紹介できるからです。
特にSESでの多様な案件経験は、整理して伝えないと一貫性がないと誤解されかねません。そのため、戦略的にアピールすることが求められるのです。
面談前には職務経歴書を詳細に作成しておきましょう。
例えば、「金融系システム開発2年、ECサイト構築1年、インフラ構築1年の経験を通じて、幅広い技術スタックと顧客対応能力を身につけました」といったように、経験を体系立てて説明できる準備が不可欠です。
また、以下のように具体的な希望条件を設定しておくことも忘れてはいけません。
- 「年収500万円以上」
- 「残業月20時間以内」
- 「自社開発中心」
その上で、週に1回程度は連絡を取り合うなど、エージェントとの良好な関係を維持していくとよいでしょう。
希望条件が曖昧だと的外れな求人紹介が続き、転職活動が長期化するリスクがあります。
面談前の自己分析と希望条件の明確化、そして面談後の定期的な進捗確認や戦略の見直し。これらを徹底することで、エージェントとの協力関係を最大限に引き出し、転職成功へと繋げることが可能です。
非公開求人を見つけるコツ
好条件の案件が多い非公開求人に出会うには、エージェントとの信頼関係を築き、自身の市場価値を高め、そして転職市場のタイミングを見計らうという、戦略的なアプローチが求められます。
非公開求人は条件の良い案件が多いため、エージェントも「この人なら」と信頼できる候補者に限定して紹介する傾向にあります。
求人を出す企業側も即戦力を求めているので、スキルや経験が不十分だと判断されると、紹介の対象から外れてしまうでしょう。
スキルシートの定期更新、新しい資格取得の報告、業務での成果共有などを通じてエージェントに自身の成長をアピールし続けることで、この人なら安心して紹介できるという信頼を獲得できます。
また、年度末や新年度、四半期末などの企業の採用活動が活発化するタイミングを狙って転職活動を行うことで、非公開求人に出会う確率が高まります。
求人には募集時期やタイミングがあるため、継続的な情報収集と迅速な対応が不可欠です。
実際に、継続的にエージェントと関係を維持していたSESエンジニアが、急遽発生した大手企業の非公開求人を即座に紹介され、競合少ない状況で転職を成功させた事例があります。
月1回のスキルアップ報告とエージェントへの近況共有、そして転職市場の繁忙期を狙った集中的な活動により、魅力的な非公開求人に出会う可能性を大幅に高められるでしょう。
まとめ
本記事では、「SESはやめとけ」と言われる理由を解説し、優良企業の見極め方や具体的な転職成功術を紹介しました。
給与が上がりにくい構造や将来への不安は、新卒や未経験からSESに入った多くのSESエンジニアが抱える悩みです。
しかし、客先常駐で培った多様な業務経験や対応力は、あなたの市場価値を高める確かな武器になります。
現状に留まるか、転職に踏み出すか。まずはこの記事を参考に自身のスキルを棚卸しし、転職エージェントとの面談を通じて納得できるキャリアプランを描くことから始めましょう。
行動こそが、未来への不安を解消する最良の一歩です。
\ 約90%が満足と回答した転職支援 /
非公開求人多数・詳細を確認




