ITストラテジストの難易度は、「資格を取ればキャリアアップできるかな」と考えるエンジニアほど気になるものです。
でも実際のところ、国家資格であるITストラテジスト試験の合格率や勉強時間を正しく把握している方は少ないのではないでしょうか?
専門性の高さから転職市場での評価が非常に高いこの資格は、合格のハードルが高い一方、取得後には正社員への転職や年収アップにも大きく貢献します。
この記事で、合格に必要な準備やポイントをしっかり押さえ、最短ルートでキャリアの可能性を広げましょう。
\ 約90%が満足と回答した転職支援 /
無料でキャリアや年収についてプロに相談するTOPICS
ITストラテジスト試験とは?難易度と合格率を解説

まずは、ITストラテジスト試験の概要や難易度、合格率などの基本情報についてご紹介します。
ITストラテジスト試験概要と合格率
ITストラテジスト試験は、情報処理推進機構(IPA)によって実施される「情報処理技術者試験」のひとつで国家試験に該当しています。
ITストラテジストは、大規模なシステム・ソフトウェア開発の上流工程において、経営者の視点で戦略立案やシステム全体の設計・管理、プロジェクトの実行を主導する専門職です。
過去5年間の合格率が15%前後を推移していることからわかるとおり、合格するには高度な知識とスキルが必要です。
| 受験資格 | 誰でも受験可能 |
| 試験の日程 | 毎年4月に開催 ※日程の詳細はIPAの公式サイトでご確認ください |
| 試験内容 | 午前Ⅰ(多肢選択式) 午前Ⅱ(多肢選択式) 午後Ⅰ(記述式) 午後Ⅱ(論述式) ※すべて1日で実施します |
| 合格率 | 2018年度:14.3% 2019年度:15.4% 2021年度:15.3% 2022年度:14.8% 2023年度:15.5% ※参考:IPA『情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 推移表』 ※2020年度はコロナ禍のため未実施 |
| 過去問 | IPAの公式サイトに掲載 |
ITストラテジスト試験と他のIT系試験の難易度を比較
ITストラテジスト試験は、「情報処理技術者試験」の中でも最難関のレベル4に分類されています。
なお、同じレベル4に分類される試験は以下の9つです。
| ITストラテジスト試験 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 |
| システムアーキテクト試験 |
| ネットワークスペシャリスト試験 |
| データベーススペシャリスト試験 |
| プロジェクトマネージャ試験 |
| ITサービスマネージャ試験 |
| システム監査技術者試験 |
| 情報処理安全確保支援士試験 |
特定の業務や職種に特化した内容の試験が多い中、ITストラテジスト試験では経営視点も含め、より広範囲な知識と経験が必要とされます。
誰でも受験可能な資格ではあるものの、将来的にCIOやCTO、ITコンサルタントを目指す方に最適な資格ともIPAの公式サイトで紹介されています。このことからも、難易度の高さは十分伺えるでしょう。
ITストラテジスト試験の難易度が高い理由
この章では、国家資格の中でも最難関の一つと言われるITストラテジスト試験が、なぜそれほど難しいのか、その理由を初心者の方にも分かりやすく解説します。
合格のハードルが高い背景には、主に以下の3つの大きな理由があります。
- 全般的なIT系の知識が必要だから
- 実践的な知識が必要な問題も出題されるから
- 全ての区分で合格点を超える必要があるから
全般的なIT系の知識が必要だから
ITストラテジスト試験の合格が難しい一つ目の理由は、求められる知識の範囲が非常に広いことにあります。この試験では、特定のプログラミング言語やサーバー技術といった専門的な知識だけではなく、ITを取り巻くあらゆる分野の知識が問われます。
なぜなら、ITストラテジストとは、企業の経営者が抱える課題を理解し、それを解決するための最適なIT戦略を立案する「経営とITの架け橋」となる存在だからです。
そのためには、AI、IoT、クラウドといった最新技術の動向はもちろん、プロジェクトを円滑に進めるためのマネジメント手法、さらには企業の財務状況を理解するための会計知識や、コンプライアンスに関わる法律の知識まで、網羅的に理解している必要があります。
一つの分野を深く掘り下げるだけでは対応できず、常に幅広い分野にアンテナを張り、体系的な知識を身につけておく姿勢が不可欠となるのです。この学習範囲の広さが、多くの受験者を悩ませる最初の壁となっています。
実践的な知識が必要な問題も出題されるから
単なる知識の暗記だけでは決して合格できない点も該当します。特に試験の後半で課される午後の記述式・論文式試験では、実務経験に裏打ちされた「生きた知恵」が試されます。
ここでは、架空の企業が抱える課題シナリオが提示され、あなた自身がITストラテジストとして、その課題をどう分析し、どのようなIT戦略で解決に導くのかを、説得力をもって論述することが求められます。
例えば「業績が低迷する小売業の競争力を強化するためのDX戦略を提案せよ」といったテーマに対し、教科書に書いてあるような一般的な解答では評価されません。「なぜそのIT技術を選ぶのか」「導入にはどのような手順を踏むのか」「投資対効果はどれくらい見込めるのか」「考えられるリスクは何か」といった点まで具体的に掘り下げ、リアリティのある提案を構築する能力が必要です。
これは知識の量を問うテストというより、課題解決能力や論理的思考力を測るコンサルティング能力のテストに近いといえるでしょう。机上の空論ではない、地に足のついた実践力が問われる点が、この試験の難易度を格段に高めています。
全ての区分で合格点を超える必要があるから
この試験が採用している「段階式選抜」という厳しい制度も難易度が高い理由の一つです。
ITストラテジスト試験は「午前I」「午前II」「午後I」「午後II」という4つの試験区分で構成されており、その全てで合格基準点(原則として満点の60%)を上回らなければ最終的な合格を手にすることはできません。
一つでも基準点に満たない科目があれば、他の科目がどれだけ高得点であっても、その時点で不合格となってしまいます。
さらに、各区分で問われる能力は異なり、午前では幅広い知識力が、午後Iでは長文を読み解く読解力と分析力が、そして午後IIでは論理的な文章構成力と表現力が試されます。そのため、得意分野で苦手分野をカバーするという戦略が通用しません。
例えば、IT知識が豊富で午前試験は難なく突破できても、午後IIの論文で時間内に考えをまとめきれずに不合格になるケースは後を絶ちません。
ITストラテジスト試験の合格に必要な勉強時間
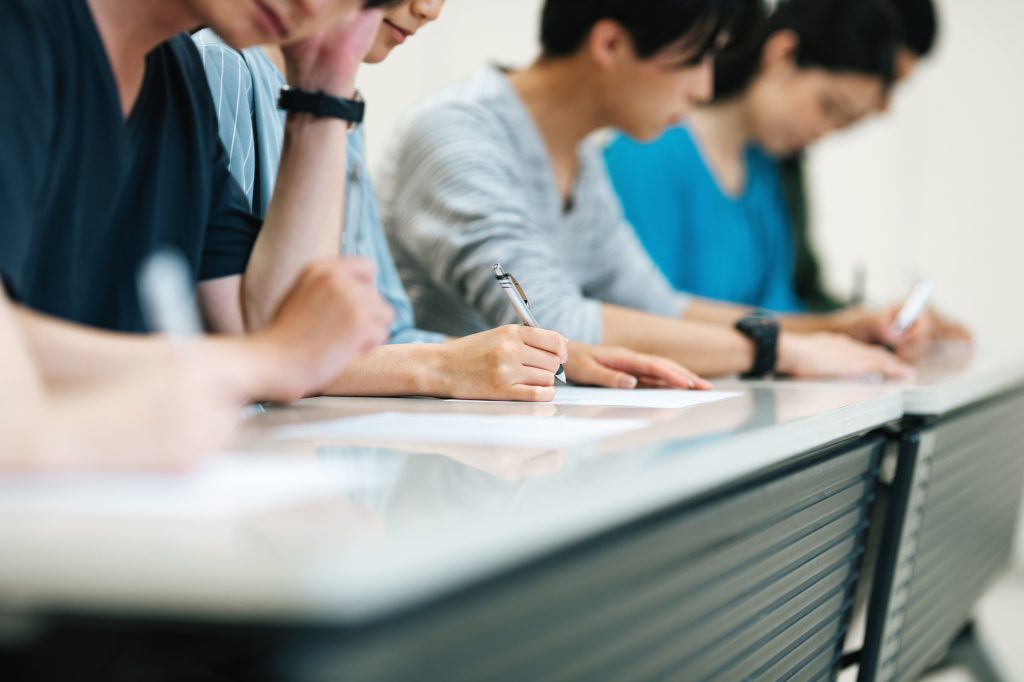
ITストラテジスト試験は「情報処理技術者試験」の最高難度の資格とされており、合格に必要な勉強時間もその他の資格試験と比較して長いのが特徴です。
個人が保有する知識・経験が異なるため、一概にはいえないものの、一般的には150〜200時間程度の勉強が必要とされます。
仕事と両立して勉強時間を確保するために、中長期的な計画で学習計画を立てることが大切です。
ITストラテジスト試験の種類と試験別の勉強方法
ここからは、ITストラテジスト試験の項目別に内容と対策を解説します。
午前Ⅰ(多肢選択式)
テクノロジー・マネジメント・ストラテジーなど、幅広い分野から出題されます。同日に開催される応用情報技術者試験から30問がピックアップされて出題されます。
4種の試験の中ではもっとも難易度が低いものの、出題範囲が広いため応用情報技術者試験の過去問を中心に幅広く知識を得ることが大切です。
| 試験時間 | 50分 |
| 出題形式 | 多肢選択式(四肢択一) |
| 出題数・解答数 | 出題数:30問 解答数:30問 |
| 合格点・基準点 | 合格点:100点 基準点:60点 |
なお、以下の条件を満たしている方は試験が免除されます。
- 応用情報技術者試験の合格者
- 高度情報処理技術者試験または情報処理安全確保支援士試験の合格者
- 高度情報処理技術者試験または情報処理安全確保支援士試験の午前Ⅰ試験で基準点を獲得した方
午前Ⅱ(多肢選択式)
セキュリティ・システム戦略・システム企画・経営戦略マネジメント・技術戦略マネジメント・ビジネスインダストリ・企業活動・法務の8分野の中から出題されます。
午前Ⅰに出題された内容よりさらに難易度が高いことに加え、最新の専門用語や時事ネタが盛り込まれる可能性が高いです。
経済紙や新聞、ニュースなどに普段から目を通しておきましょう。
| 試験時間 | 40分 |
| 出題形式 | 多肢選択式(四肢択一) |
| 出題数・解答数 | 出題数:25問 解答数:25問 |
| 合格点・基準点 | 合格点:100点 基準点:60点 |
午後Ⅰ(記述式)
3問の中から2問を選んで回答します。主に企業の課題や取り組み事例などが出題され、指定の文字数で課題解決のための対応策を記述します。
近年は、IoTやAIなどの最先端技術に関する問題が出題される傾向にあります。
基本的な知識を身につけておくのはもちろん、ITで企業の課題を解決したモデルケースを幅広く学ぶとよいでしょう。
| 試験時間 | 90分 |
| 出題形式 | 記述式 |
| 出題数・解答数 | 出題数:3問 解答数:2問 |
| 合格点・基準点 | 合格点:100点 基準点:60点 |
午後Ⅱ(論述式)
2問の中から1問を選んで解答します。解答の結果はA~Dで評価され、Aランクのみが合格となります。午後Ⅰに比べて指定文字数が多い点が特徴です。
専門的な知識だけでなく、文章構成力や論理的思考力が大いに求められます。また、独創性や先見性もAランクをもらうために必要です。
サイエンスやファイナンスなど、幅広い分野の情報を常日頃から収集し、独創性や先見性を鍛えましょう。また、レポートやコラムで文章構成力を養うなど、多面的な対策が不可欠です。
| 試験時間 | 120分 |
| 出題形式 | 論述式 |
| 出題数・解答数 | 出題数:2問 解答数:1問 |
| 合格点・基準点 | A~Dランクで評価され、Aランクのみ合格 |
ITストラテジスト試験に合格するコツ
この章では、ITストラテジスト試験に合格するための具体的なコツについて紹介します。
ITストラテジスト試験は、IT系の国家資格の中でも最難関レベルに位置付けられており、合格するためには戦略的な学習が不可欠です。
- 学習スケジュールを立てる
- 過去問の分析や対策を徹底する
- 筆記試験に慣れる
- 独学にこだわりすぎない
学習スケジュールを立てる
ITストラテジスト試験の合格を目指す上で、何よりも先に着手すべきなのが、自分だけの学習スケジュールを作成することです。
この試験は年に一度しかチャンスがなく、合格には実務経験者でも150時間以上の学習が必要と言われています。そのため、行き当たりばったりで勉強を始めても、広大な試験範囲を前に途方に暮れてしまうでしょう。
まずは試験日から逆算し、例えば4ヶ月前から学習を開始する計画を立てます。最初の1ヶ月は参考書を読み込み、基礎知識を固めると同時に午前問題の対策を開始。
2ヶ月で、配点の高い午後Ⅰ(記述式)と午後Ⅱ(論文)の対策に着手し、自身の業務経験を論文のネタとして整理します。
そして最後の1ヶ月は、本番と同じ時間配分で過去問を解くなど、実践的な練習に集中します。このように、長期的な視点でマイルストーンを定め、週単位、日単位のタスクに落とし込むことで、着実に合格へと近づくことができます。
過去問の分析や対策を徹底する
ITストラテジスト試験において、過去問は単なる力試しではなく、合格への最短ルートを示す「最高の教材」です。
なぜなら、過去問には出題の傾向や、評価される思考プロセス、解答に求められる文章構成力など、合格に必要なエッセンスが凝縮されているからです。
特に午前問題は過去問からの再出題率が高いため、最低でも5年分は繰り返し解き、選択肢だけでなく関連知識まで完全に理解することが重要です。
一方、午後問題はより深い分析が求められます。午後Ⅰの記述式では、解答例を見るだけでなく「なぜその答えになるのか」を問題文の根拠と照らし合わせて論理的に解明する作業が不可欠です。
午後Ⅱの論文では、合格者の論文を参考に「評価される構成の型」を学び、様々なテーマに対して自身の経験をどう当てはめるかシミュレーションを重ねましょう。
ただ解いて終わりにするのではなく、「出題者は何を問いたいのか」という視点で一問一問を深く掘り下げることが、合格の鍵を握っています。
筆記試験に慣れる
ITストラテジスト試験の午後問題は、知識を問うだけでなく、時間内に論理的な文章を手で書き上げる「筆記スキル」そのものが試されます。
普段の業務でPC入力に慣れていると、長文を手書きする行為自体が大きな負担となり、時間配分の失敗や、簡単な漢字が出てこないといった思わぬ壁にぶつかります。
このスキルは、本番を想定した地道な練習でしか身につきません。具体的には、まず午後Ⅰは1問45分、午後Ⅱは120分と時間を厳密に計り、問題文の読解から骨子の作成、執筆、見直しまでの一連の流れを体に染み込ませます。
そして、必ずPCではなく解答用紙とペンを使って、実際に手を動かして答案を作成する練習を繰り返してください。2時間で3000字近い論文を書き上げる筆力を養い、自分に合った疲れにくいペンを見つけておくことも大切です。
こうした実践的な練習を通して、「知っていること」を「時間内に書き切れること」へと昇華させることが、合否を分ける大きなポイントになります。
独学にこだわりすぎない
ITストラテジストは最難関の国家資格であり、その合格への道のりは平坦ではありません。特に、独学で学習を進めることには限界がある点を理解しておくべきです。
最大の壁となるのが、午後Ⅱの論文試験です。自分の書いた論文が、論理的に破綻していないか、ITストラテジストとして求められる視点が含まれているかを客観的に評価することは、独りでは極めて困難です。
この課題を解決するために、独学に固執せず、予備校や通信講座が提供する外部サービスの活用を柔軟に検討しましょう。例えば、専門講師による「論文添削サービス」を利用すれば、自分では気づけなかった弱点を的確に指摘してもらえ、合格レベルの答案へと改善できます。
また、体系的に要点がまとめられた「オンライン講座」は、広大な試験範囲を効率良く学ぶ上で大きな助けとなるでしょう。合格という目標達成のためには、時に外部の力を借りるという戦略的な判断も必要不可欠なのです。
ITストラテジスト試験は「役に立たない」と言われる理由
この章では、高難易度の国家資格であるITストラテジストが、一部で「役に立たない」と見なされる理由について解説します。
- 資格がなくても業務はできるから
- 実務経験の方が重視される傾向があるから
資格がなくても業務はできるから
ITストラテジストの業務は、結論から言うと資格を持っていなくても行うことが可能です。
なぜなら、医師や弁護士のように法律で「資格を持つ者だけがその業務を行える」と定められた業務独占資格ではないためです。
また、資格がなければ「ITストラテジスト」と名乗れないわけでもありません。実際に、企業内でIT戦略を担う人材やITコンサルタントが、資格なしでその役割を立派に務めているケースは数多く存在します。
例えば、長年IT部門や経営企画部門で経験を積んだ方が、自社のDX推進リーダーとして経営戦略に沿ったIT投資計画を策定し、経営層へ提言する場面を想像してみてください。その方は資格を持っていなくても、現場で培った知見と経験を基に、実質的なITストラテジストとして活躍しています。
とはいえ、必須ではないものの、資格の学習は質の高い戦略を立案するための強力な武器となり得るでしょう。
実務経験の方が重視される傾向があるから
IT戦略やコンサルティングの世界では、資格の有無よりも「何を成し遂げたか」という具体的な実務経験や実績がより高く評価される傾向が強いといえます。
その理由は、企業のIT戦略立案が、単なる技術知識だけでは完遂できないからです。そこには業界特有の商習慣、長年かけて形成された企業文化、そして組織内の複雑な人間関係といった、ペーパーテストでは決して測れない要素が深く関わってきます。
採用する企業や仕事を依頼するクライアントからすれば、机上の知識が豊富な人材より、困難なプロジェクトを最後までやり遂げた経験や、ITを活用して事業課題を解決した実績を持つ人材に魅力を感じるのは当然のことです。
実際に、IT戦略部長などのハイクラスな求人では、必須条件に「事業会社でのIT企画経験10年以上」といった実務経験が掲げられ、ITストラテジスト資格は「歓迎スキル」にとどまることが少なくありません。
ただし、経験と資格は対立するものではなく、むしろ相乗効果を生み出します。経験豊富な方が資格を得れば、自身のスキルを客観的に証明でき、キャリアの価値を一層高められます。
ITストラテジスト試験に合格するメリットとは?

非常に難易度が高いITストラテジスト試験ですが、合格することでどのようなメリットが得られるのでしょうか?
ここでは、ITストラテジスト試験に合格すると得られる主なメリットを5つご紹介します。
- 高度なIT知識を持っている証明になる
- 昇進・昇給に有利に働く
- 転職活動に役立てられる
- 日本ITストラテジスト協会に入会できる
- 市場価値が高いIT人材であることを示せる
高度なIT知識を持っている証明になる
ITストラテジスト試験は、IT戦略立案・システム設計・プロジェクト管理など、情報技術に関する幅広い知識と高度なビジネススキルを要求される試験です。
そのため、試験に合格することは、高度なIT知識を持ち、複雑な問題を解決できる能力を有していることの証明となります。
昇進・昇給に有利に働く
ITストラテジストの資格は、業界内で高く評価されています。資格を取得することで昇進や昇給のチャンスが増える可能性があります。
また、企業によっては、ITストラテジスト試験に合格した方を対象にした資格インセンティブを設けているところもあるでしょう。
転職活動に役立てられる
ITストラテジストの資格には「実務経験5年分のスキルに相当する価値がある」といわれています。
転職市場においても大きなアドバンテージになり、キャリアアップや年収アップをかなえる際に役立つ可能性が高いです。
ITストラテジスト試験に合格したら、ぜひ選考の場で面接官にアピールしてください。
日本ITストラテジスト協会に入会できる
ITストラテジストの資格を取得できれば、日本ITストラテジスト協会に入会できます。
日本ITストラテジスト協会は、情報化戦略・情報化計画についての情報交換や人脈形成、実務能力の強化を目的とした団体です。
入会することで、社外の人とのつながりをつくりやすくなり、今後のキャリア形成に活かせるでしょう。
市場価値が高いIT人材であることを示せる
ITストラテジスト資格は、自身の市場価値を客観的な形で証明し、キャリアの可能性を大きく広げるための強力な武器となります。
最大の理由は、その希少性と証明される能力の高さにあります。この試験の合格率は例年15%前後と極めて低く、誰もが簡単に取得できる資格ではありません。
そのため、保有しているだけで、高度な知識とスキルを求める学習意欲の高い人材であるという評価に繋がります。さらに重要なのは、この資格が証明する能力です。
それは単なるITの専門知識に留まらず、経営者の視点で事業戦略を深く理解し、それを実現するためのIT戦略を策定・提案・推進できる「超上流工程」のスキルです。
こうした能力を持つ人材は、企業のDX推進や事業変革の核となるため、転職市場での需要が非常に高い傾向にあります。結果として、ITコンサルタントや事業会社のCIO(最高情報責任者)候補といった、より責任が大きく、高い報酬が期待できるポジションへの道が拓きやすくなります。
ITストラテジストの仕事内容と難易度
ITストラテジストとは、単にITに詳しい人ではありません。企業の経営者が抱える課題を深く理解し、それを解決するための最適なIT戦略を立案・実行する「経営とITの橋渡し役」です。
その仕事内容は多岐にわたりますが、主に以下の4つの役割を担い、企業の成長と競争力向上に貢献します。
- 事業戦略・IT戦略の策定
- システム開発や運営の統括
- モニタリングやコントロール
- 最新の市場動向の調査
事業戦略・IT戦略の策定
ITストラテジストの最も重要かつ中心的な仕事は、企業の経営課題を解決し、事業を成功に導くためのIT戦略を策定することです。
例えば、ある製造業で「熟練の職人が次々と引退し、長年培った技術の継承が難しい」という深刻な経営課題があったとします。このときITストラテジストは、製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集(IoT)し、そのデータを人工知能(AI)で分析。若手の作業員でも熟練工と同じレベルの品質で作業できるよう支援するシステムを導入する、といった戦略を立案します。
このように、ITはあくまで経営課題を解決するための手段です。そのため、ITストラテジストには技術知識はもちろん、経営や財務、マーケティングといった幅広いビジネス知識と、複雑な問題を整理し、解決策を導き出す論理的な思考力が求められます。
システム開発や運営の統括
どれほど優れたIT戦略を立てても、それが「絵に描いた餅」で終わってしまっては意味がありません。策定した戦略を具体的なシステムとして形にし、確実に実行まで導くのがこのフェーズの役割です。
ITストラテジストは、戦略を実現するためのシステム開発プロジェクト全体を統括し、推進します。例えば、全社で利用する新しい顧客管理システム(CRM)を導入するプロジェクトを考えてみましょう。
ITストラテジストは、まず経営層や営業、マーケティングといった各部門から「どんな機能が欲しいか」という要求を丁寧にヒアリングし、それをシステムの要件に落とし込みます。その上で、複数のITベンダーからの提案を比較検討し、最適なパートナーを選定します。
プロジェクトが始まった後も、プロジェクトマネージャと密に連携を取りながら、戦略の目的から逸れずに計画通り進んでいるかを管理し、経営陣に進捗を報告します。
自らプログラミングを行うわけではありませんが、開発の全工程を深く理解し、多くの関係者を動かしてプロジェクトを成功に導く、高度なマネジメント能力が不可欠です。
モニタリングやコントロール
IT戦略は、システムを導入して完了ではありません。むしろ、導入してからが本当のスタートです。
ビジネスを取り巻く環境やお客様のニーズは常に変化していくため、導入したシステムが本当に狙い通りの効果を上げているかを継続的に見守り(モニタリング)、状況に応じて計画を修正していく(コントロール)必要があります。
これは、航海士が羅針盤を常に確認しながら、目的地に向かって船の舵を取る作業に似ています。例えば、新しいマーケティング支援ツールを導入した場合、「見込み客の問い合わせが月100件増える」といった具体的な目標(KPI)を設定します。
そして毎月その数値をチェックし、もし目標に届かなければ「なぜだろう?Webサイトのコンテンツが魅力ないからか?ターゲット設定がずれているのか?」と原因を分析し、マーケティング部門に改善策を提案します。
このようなPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回し続けることで、戦略の効果を最大化し、企業の貴重なIT投資が無駄になるのを防ぐことができます。
最新の市場動向の調査
企業の成長を持続させ、競争で勝ち残っていくためには、常に世の中の新しい動きにアンテナを張っておくことが欠かせません。
ITストラテジストは、AIやIoT、クラウドといった最新技術の動向はもちろん、競合他社がどのようなIT戦略を打ち出しているか、世界ではどのような新しいビジネスモデルが生まれているかを常に調査・分析しています。
技術革新のスピードが非常に速い現代では、昨日まで想像もしなかったような新しいテクノロジーが、ある日突然、業界の常識を根底から覆してしまう可能性があります。そうした変化をいち早く察知し、自社にとっての「脅威」を回避しつつ、それを「成長の機会」として活用する道筋を考えるのがこの役割の重要な点です。
例えば、最近話題の生成AIについて、自社のカスタマーサポート業務を効率化できないか(守りの活用)、あるいはこれまでにない新しいサービス開発に繋げられないか(攻めの活用)を調査し、経営陣に具体的な活用法とリスクを報告します。
まとめ
ITストラテジスト試験は、「情報処理技術者試験」の中でも難易度が高い試験です。
合格するためには業務での経験はもちろん、幅広い知識が必要です。そのため、中長期的な視野で学習計画を立てる必要があります。
資格を得れば市場価値を高めることができ、昇進・昇格や転職にも有利に働くでしょう。今回ご紹介した内容を参考に、ITストラテジスト試験の受験を検討してみてください。
\ 転職者の約8割が年収アップに成功 /
高単価案件を今すぐチェック(無料)




