「ITアウトソーシングはやめとけ」という声を聞いて迷っていませんか?
新卒で内定を受けたものの将来に不安を感じている方、SES常駐で数年働いても年収やキャリアの伸び悩みに悩む方は少なくありません。
配属ガチャや単調な作業への懸念から転職を諦める必要はありません。
実際には、自社開発企業や社内SE、SIerなど魅力的な選択肢が豊富に存在し、正しい戦略さえあれば確実にキャリアアップを実現できます。
この記事では、ITアウトソーシングの真実を包み隠さず解説し、あなたに最適な転職戦略をお伝えします。
\ 転職者の約8割が年収アップに成功 /
高単価案件を今すぐチェック(無料)TOPICS
ITアウトソーシングとは何か

ITアウトソーシングでのキャリアを検討する際、なぜ「やめとけ」という意見があるのか疑問に思うかもしれません。
この章では、そうした声の背景にある業界特有の仕組みを3つの側面から客観的に解説します。
- 下請け構造と契約形態
- 配属の仕組みと案件ガチャ
- 給与体系と評価の特徴
仕組み(1)下請け構造と契約形態
ITアウトソーシング業界を理解する上で、まず知っておくべきなのが多重下請け構造です。
これは、元請けとなる発注元企業から受注した案件が、一次請け、二次請け、三次請けといった複数の企業を経由して、最終的に現場で働くエンジニアへと流れていく商流の仕組みを指します。
この構造は、大規模なプロジェクトに必要な人員を迅速に確保するため、また各社の得意分野を活かすために古くから業界で定着してきました。
商流が深くなるほど、プロジェクトに関わる企業の数が増えるのが特徴です。
また、エンジニアと所属企業、そして配属先企業との間で結ばれる契約形態も重要な要素となります。
ITアウトソーシングで最も一般的なのは準委任契約であり、これは成果物の完成責任を負うのではなく、定められた業務を適切に遂行する責任を負う働き方です。
その他にも、完成責任を負う請負契約や、特定の業務委託契約など、案件の性質によって異なる契約形態が用いられます。
これらの契約形態の違いが、エンジニアの業務範囲や責任の所在を決定づける重要な要素となるのです。
| 契約形態 | 主な特徴 | 責任の所在 |
| 準委任契約 | 業務の遂行に対して対価が支払われる | 業務を適切に遂行する責任(善管注意義務) |
| 請負契約 | 成果物の完成に対して対価が支払われる | 成果物を完成させる責任(契約不適合責任) |
| 業務委託契約 | 特定の業務全般を委託する包括的な契約 | 契約内容により異なる |
このように、多重下請け構造と複数契約形態の組み合わせが、ITアウトソーシング業界の複雑さを生んでいます。
仕組み(2)配属の仕組みと案件ガチャ
ITアウトソーシングにおけるエンジニアの配属プロセスは、主に所属企業の営業担当者によって進められます。
自社で雇用しているエンジニアのスキルや経験をまとめたスキルシートを、案件を持つクライアント企業や上位のIT企業に提案し、面談を経て契約が成立すると配属が決定するというのが基本的な流れです。
この仕組みのポイントは、エンジニア個人の希望だけでなく、営業担当者の判断が配属先の決定に大きく影響する点です。
営業担当者は、企業の売上を確保するため、エンジニアの待機期間をなくし、できるだけ早く、そして契約条件の良い案件に配属させることを目指します。
そのため、エンジニア本人が希望する技術領域やキャリアプランと、営業担当者が優先する「成約のしやすさ」との間に、時としてズレが生じてしまうのです。
このような、自身の希望や適性と必ずしも一致しない案件に配属される可能性があり、配属先を自分では選べない状況は、俗に「案件ガチャ」や「配属ガチャ」と呼ばれています。
もちろん、エンジニアのキャリアプランを深く理解し、最適な案件を提案しようと尽力する営業担当者も数多く存在します。
しかし、構造上、営業担当者の目標とエンジニアの希望が常に一致するとは限らないという点は、この業界の仕組みを理解する上で重要な側面です。
仕組み(3)給与体系と評価の特徴
ITアウトソーシングで働くエンジニアの給与体系と評価制度は、客先常駐という働き方と密接に関連しています。
給与の源泉となるのは、配属先企業が所属企業に対して支払う契約単価、つまりエンジニア一人あたりの月額費用です。
所属企業は、この契約単価から自社の利益や経費を差し引いた金額をエンジニアの給与として支払います。
そのため、エンジニアの給与を上げるためには、契約単価そのものを上げることが最も直接的な方法です。
次に評価制度ですが、これも客先常駐ならではの特徴があります。
エンジニアの日々の働きぶりを直接見ているのは、自社の上司や人事担当者ではなく、配属先企業の担当者です。
したがって、評価の主な情報源は、配属先担当者が記入する評価シートや、定期的な面談でのヒアリングが中心となります。
自社は、その客観的評価を基にして、昇給や賞与の査定を行うのが一般的です。
この仕組みは、現場での貢献が直接評価に結びつきやすいという側面がある一方で、評価基準が配属先の文化や担当者の主観に左右される可能性も内包しています。
契約更新のタイミングで単価交渉が行われ、その結果が給与に反映されるというサイクルが、この業界の基本的な給与・評価システムであると理解しておくとよいでしょう。
ITアウトソーシングのメリット

業界の構造的な課題が指摘される一方で、ITアウトソーシングには、特にキャリアの初期段階において確かなメリットが存在します。
ここでは、ITアウトソーシングを活用することで得られる4つの代表的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
- 未経験からIT業界に入りやすい
- 多様な現場で経験を積める
- 残業が少なくワークライフバランスを保ちやすい
- 将来のキャリアの選択肢が広がる
メリット(1)未経験からIT業界に入りやすい
ITアウトソーシングは、実務未経験者がIT業界へ参入しやすい職種の一つです。
多くのITアウトソーシング企業は、旺盛な人材需要を背景に、未経験者向けの採用枠と育成プログラムを設けているのが大きな特徴です。
自社開発企業などでは即戦力となる実務経験が求められることが多い中、ITアウトソーシング企業では入社後に1ヶ月から3ヶ月程度の研修を実施し、プログラミングの基礎やITインフラの基本知識を学べる機会を提供している場合が多くあります。
これは、テスト工程やシステムの運用・監視といった、比較的定型的な業務からスタートできる案件を多数確保しているビジネスモデルだからこそ可能な仕組みです。
採用選考においても、現時点での技術スキルだけでなく、論理的思考力や学習意欲、コミュニケーション能力といったポテンシャルが重視される傾向が強いと考えられます。
そのため、文系出身者や他業種からのキャリアチェンジを目指す方々にとっても、選考を通過できる可能性は十分にあります。
まずは実務経験を積むことを最優先に考え、IT業界でのキャリアをスタートさせたいと考える人にとって、この参入障壁の低さは非常に大きなメリットです。
メリット(2)多様な現場で経験を積める
一つの企業に所属しながら、多種多様な業界や技術に触れる機会を得られることは、ITアウトソーシングならではのメリットです。
自社開発企業では自社のサービスやプロダクトに特化して経験を積むのが一般的ですが、ITアウトソーシングでは、契約するクライアントによって全く異なる環境で働くことができます。
例えば、最初の1年は大手金融機関の基幹システム開発に携わり、次の2年間は製造業の生産管理システムの刷新プロジェクトに参加し、その次は官公庁のインフラ構築案件を担当するといったキャリアパスを描くことも可能です。
これにより、特定の業界知識と技術スキルを掛け合わせることで、自身の市場価値を高めていくことができます。
技術的な側面でも同様で、プロジェクトごとに異なるプログラミング言語、フレームワーク、クラウドサービスに触れるチャンスがあります。
Webアプリケーション開発でJavaやReactを学んだ後に、クラウド移行プロジェクトでAWSやAzureのスキルを身につけるなど、短期間で幅広い技術スタックを経験できる可能性を秘めているのです。
特定の技術領域に固執せず、まずは様々な経験を積んでから自身の専門分野を定めたいと考えるエンジニアにとって、この環境は最適な学びの場となるでしょう。
メリット(3)残業が少なくワークライフバランスを保ちやすい
ワークライフバランスを重視する方にとって、ITアウトソーシングの働き方はメリットです。
これは客先常駐という勤務形態の特性と、準委任契約という契約形態の性質に起因します。
まず、エンジニアは配属先であるクライアント企業の就業規則やルールに従って勤務するため、労働時間もクライアント企業の規定に準じます。
特に大手企業のプロジェクトでは、コンプライアンス意識が高く、勤怠管理が厳格に行われているため、サービス残業が発生しにくく、過度な長時間労働を強いられるケースは少ないでしょう。
また、SES契約で一般的な準委任契約は、成果物の完成ではなく、契約時間内での業務遂行を目的としています。
そのため、納期に追われて無理な残業や休日出勤をするといった、請負契約に多い働き方とは異なり、比較的スケジュールをコントロールしやすいのが特徴です。
もちろん、プロジェクトの繁忙期やトラブル発生時には残業が必要になることもありますが、原則として契約で定められた時間を超える業務は要求されにくい構造になっています。
プライベートの時間も大切にしながら、エンジニアとしてのキャリアを継続したいと考える人にとって、この働きやすさはメリットです。
メリット(4)将来のキャリアの選択肢が広がる
ITアウトソーシングで得られる多様な経験は、その後のキャリアの選択肢を大きく広げます。
複数のプロジェクトに参加する過程で、様々な企業の文化や働き方に触れることができるため、将来自分がどのような環境で働きたいのかを具体的にイメージするのに役立ちます。
例えば、大手SIerのプロジェクトマネジメント手法を学んだ経験は、将来SIerへの転職を考える際に有利に働くでしょう。
また、事業会社のシステム部門でユーザーと直接やり取りした経験は、社内SEへのキャリアチェンジを目指す際の大きなアピールポイントになります。
技術面においても、幅広いスキルを習得することで、特定の技術に依存しない柔軟なキャリア設計が可能です。
さらに、様々な現場で働くことは、多様なバックグラウンドを持つエンジニアやビジネスパーソンとの人脈を築く絶好の機会でもあります。
これらの経験と人脈は、将来的にフリーランスとして独立を検討する際にも役立つ可能性がありますが、それ以上に、より条件の良い企業へ転職したり、新たな分野へ挑戦したりする際の選択肢を広げてくれる貴重な財産となるはずです。
特定のキャリアに縛られず、幅広い可能性の中から自分に合った道を選びたいと考える人にとって、ITアウトソーシングは有効なキャリアステップとなり得るのです。
ITアウトソーシングのデメリット
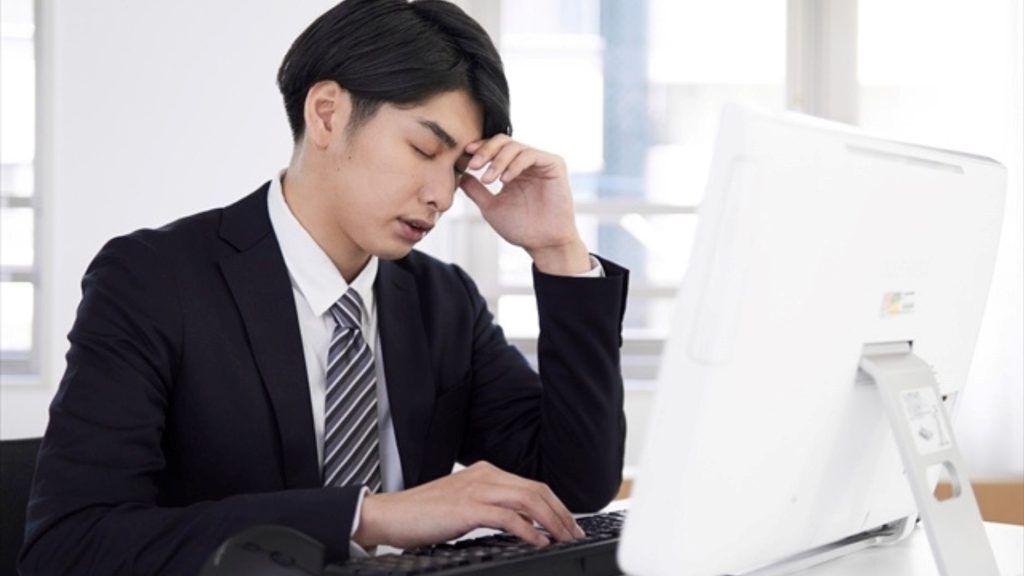
ITアウトソーシングにはメリットがある一方で、「やめとけ」という意見の根拠となる構造的な課題も存在します。
キャリアを選択する上で後悔しないためには、これらのデメリットを事前に正しく理解しておくことが不可欠です。
- 年収が低く昇給が伸びにくい
- 雇用が不安定で契約切りリスクがある
- 現場ガチャで単純作業が多い
- 専門スキルが身につきにくい
- 人間関係や職場環境の問題が起きやすい
デメリット(1)年収が低く昇給が伸びにくい
ITアウトソーシング業界で働くエンジニアが直面する最も大きな課題の一つが、年収の低さと昇給の困難さです。
この問題の根源には、業界特有の多重下請け構造があります。
発注元企業から支払われた費用は、商流を経るごとに中間マージンとして各社に差し引かれるため、末端で働くエンジニアに還元される金額はどうしても少なくなります。
例えば、元請け企業が月額80万円で発注した案件でも、複数の仲介企業を経由することで、最終的にエンジニアの給与の原資となる金額は半分近くまで減少してしまうケースも珍しくありません。
この構造は、個々のエンジニアの給与水準を業界全体として押し下げる要因となっています。
| 職種 | 平均年収の目安 |
| SESエンジニア | 約500万円 |
| SIer | 約550万円 |
| 社内SE | 約500万円 |
各種調査によると、SESを含むITアウトソーシングエンジニアの平均年収は、社内SEと同程度である一方、SIerと比較すると低い水準にとどまる傾向が見られます。
また、昇給が伸び悩む構造的な理由も存在します。
給与を上げるためには契約単価を上げる必要がありますが、そのためには配属先企業との交渉が不可欠です。
しかし、一度決まった単価を上げることは容易ではなく、景気の動向やプロジェクトの予算によっては、逆に単価が引き下げられることさえあります。
自身のスキルアップが必ずしも給与に直結しないこの仕組みは、長期的な年収向上を目指す上で大きな障壁となり得るのです。
※参考:レバテックキャリア「SESの給料・年収が上がらない理由は6つ!昇給する方法なども紹介」
レバテックキャリア「大手SIerの売上高&平均年収ランキング一覧!特徴も解説」
レバテックキャリア「社内SEの平均年収・給料の統計」
デメリット(2)雇用が不安定で契約切りリスクがある
正社員として雇用されていても、実質的な雇用の安定性が低い場合がある点も、ITアウトソーシングの大きなデメリットです。
多くのSES契約は、3ヶ月や6ヶ月といった短期間で更新を繰り返す形態をとっています。
これは、クライアント企業がプロジェクトの状況や予算に応じて、人員を柔軟に調整できるようにするためです。
その結果、エンジニアは常に契約が更新されない、いわゆる「契約切り」のリスクに晒されることになります。
プロジェクトの終了、予算の削減、あるいはクライアント企業の経営方針の変更など、自身のパフォーマンスとは無関係な理由で、ある日突然、現場を離れなければならなくなる可能性はゼロではありません。
契約が終了し、次の配属先がすぐに見つからない場合、「待機」と呼ばれる状態になります。
この待機期間中は、給与が基本給の満額ではなく、労働基準法で定められた休業手当に準じた割合に減額される企業も少なくありません。
待機が長期化すれば収入は大幅に減少し、生活への影響も大きくなります。
特に市況が悪化した局面では、新たな案件が見つかりにくくなるため、このリスクはさらに高まる傾向があります。
このように、常に契約終了のリスクと隣り合わせである働き方は、長期的なキャリアプランやライフプランを考える上で大きな不安要素となるでしょう。
デメリット(3)現場ガチャで単純作業が多い
自身のキャリアプランと無関係な業務に長期間従事させられるリスク、いわゆる「現場ガチャ」の問題も深刻です。
ITアウトソーシングでは、配属先が所属企業の営業担当者によって決定されるため、その判断が必ずしもエンジニアの希望や適性を最優先にするとは限りません。
営業担当者の目標は、自社の売上を最大化することです。
そのため、エンジニアのスキルやキャリアプランに合致していなくても、契約が取りやすい案件や、単価の高い案件を優先する場合があります。
その結果、次のようなミスマッチが発生することがあります。
| 希望していたキャリア | 実際の配属例と業務内容 |
| 最新のWeb技術を学ぶWeb開発 | 大手通信会社のコールセンターで1年以上の電話対応・事務処理 |
| PythonやSQLを活かすプログラミング | Excelでのデータ入力・集計作業を数年間継続 |
こうした単純作業やITスキルを必要としない業務に一度配属されると、スキルシートにその経歴しか書けなくなり、次の案件も類似の単純作業を紹介されやすくなるという負のループに陥る危険性があります。
キャリア形成において最も重要な若手時代を、スキルアップにつながらない業務で過ごしてしまうことは、エンジニアとしての将来に大きな影を落とすことになりかねません。
デメリット(4)専門スキルが身につきにくい
ITアウトソーシングの働き方は、ひとつの技術を深く追求する専門性を高める上で、不利に働くことがあります。
多くの案件、特に未経験や経験の浅いエンジニア向けに用意されているのは、システム開発の工程の中でも下流に位置付けられる業務が中心です。
具体的には、完成したシステムのテスト、稼働中のシステムの運用・監視、ユーザーからの問い合わせ対応といった業務です。
これらの業務もITシステムを支える上で不可欠ですが、要件定義や基本設計、アーキテクチャの選定といった、より上流の工程に携わる機会は限られています。
そのため、システム設計の意図や、ビジネス課題を技術で解決する思考力など、上流工程で求められるスキルを磨く機会が少なくなります。
また、3ヶ月から半年といった短いサイクルで現場が変わることも、専門性の構築を難しくする一因です。
ようやく業務やシステムに慣れてきた頃に次のプロジェクトへ異動となるため、どうしても知識やスキルが「浅く広く」なります。
複数のプログラミング言語に触れた経験はあっても、そのどれもが基本的な文法を理解しているレベルに留まり、パフォーマンスチューニングや大規模な設計といった深い知見を得られないでしょう。
技術の進化が速いIT業界において、代替可能なスキルしか持たないエンジニアは市場価値を高めることが難しく、長期的なキャリア形成において大きな不安を抱えることになります。
デメリット(5)人間関係や職場環境の問題が起きやすい
客先常駐という働き方は、人間関係の構築や職場環境の面で特有の難しさを抱えています。
エンジニアは、業務指示を出す「配属先企業」、雇用契約を結ぶ「所属企業(自社)」、そして案件を調整する自社の「営業担当者」という三者の間に立つことになります。
この三者の利害や要求が必ずしも一致しないため、板挟みになってストレスを感じることが少なくありません。
例えば、配属先からは残業を求められても、所属企業からは契約時間を遵守するよう指示されるといった矛盾した状況が発生し得ます。
また、配属先では「外部の人間」として扱われ、正社員との間に見えない壁を感じたり、重要な情報が共有されなかったりといった疎外感を覚えることもあります。
一方で、所属企業への帰属意識も希薄になりがちです。
月に一度の帰社日以外は自社の社員と顔を合わせる機会がなく、キャリアの相談ができる上司や、気軽に話せる同僚がいないという孤独な状況に陥るエンジニアもいます。
職場環境が数ヶ月から数年単位で頻繁に変わるため、腰を据えて長期的な人間関係を築いたり、尊敬できるメンターを見つけて指導を受けたりする機会も限られます。
このように、安定した人間関係や職場環境を築きにくい点は、日々の業務のモチベーション維持や、長期的なキャリア形成において精神的な負担となるのです。
優良ITアウトソーシング企業の見分け方

ITアウトソーシング業界の課題を理解した上で、次に重要となるのが、それらのデメリットを回避できる優良企業をいかにして見極めるかです。
ここでは、入社後のミスマッチを防ぎ、自身のキャリアを大切にしてくれる企業を見分けるための3つの具体的なチェックポイントを解説します。
- 契約条件と待遇面の確認
- 面接で必ず聞くべき質問
- 教育制度と案件選択の自由度
見極め(1)契約条件と待遇面の確認
優良なITアウトソーシング企業を見分ける上で、最も客観的で重要な指標となるのが、契約条件と待遇に関する情報の透明性です。
特に以下の3点は、企業のエンジニアに対する誠実さを測るバロメーターとなります。
- 還元率
- 商流
- 待機時の保障
還元率とは、クライアントが支払う契約単価のうち、どれだけの割合がエンジニアの給与や福利厚生に充てられるかを示す数値です。
この数値が高いほど、エンジニアへの利益配分を重視している企業と判断できます。
次に重要なのが商流、つまり直請け案件の比率です。
直請け比率が高い企業は、中間マージンによる搾取が少なく、エンジニアはより高い単価の恩恵を受けやすくなります。
最後に、待機時の給与保障も必ず確認すべき項目です。
待機期間中も給与を100%保障する企業は、エンジニアの生活安定を第一に考えている証拠です。
| 確認すべき 待遇項目 | 優良企業の 傾向 | なぜ重要か (回避できるデメリット) |
| 還元率 | 70%以上を目安とし、具体的な数値を公開している | 年収が低く、昇給が伸び悩むリスクを軽減 |
| 直請け案件比率 | 50%以上を目安とし、主要顧客を開示している | 多重下請けによる中間搾取を回避 |
| 待機時の給与保障 | 給与の100%を保障している | 雇用の不安定さや収入減のリスクに備える |
| 平均年齢・離職率 | 平均年齢が30代以上、3年後離職率が30%未満 | 長期的に働きやすい環境か判断する材料 |
これらの情報は、企業の採用サイトだけでなく、可能であればIR情報や有価証券報告書といった客観的な資料でも確認することが重要です。
面接でこれらの数値について質問した際に、明確な回答を避けたり、「業界平均レベル」といった曖昧な言葉で濁したりする企業は、慎重に判断する必要があるでしょう。
見極め(2)面接で必ず聞くべき質問
面接は、企業が候補者を見極める場であると同時に、候補者が企業を見極めるための絶好の機会です。
特にITアウトソーシング企業の場合、入社後のキャリアを左右する「配属」と「評価」に関する透明性を確かめるために、核心を突いた質問をするとよいでしょう。
「現場ガチャ」や評価の不透明性といったリスクを回避するため、以下の表を参考に、具体的な回答を引き出すことを意識しましょう。
単に質問するだけでなく、その回答が具体的か、実績に基づいているか、そして誠実であるかを見極めることがポイントです。
例えば、「昇給実績」について質問した際に、具体的な昇給率や金額のレンジを提示できる企業は、評価制度が機能している可能性が高いと判断できます。
| 質問カテゴリ | 確認すべきポイント(具体的な質問例) |
| 配属について | 紹介を検討している具体的な案件(クライアント名、業界、事業内容)担当する工程の割合(開発・運用・テストなど)案件選択における本人の希望の反映プロセス |
| 評価・待遇について | 昇給の具体的な評価基準と評価プロセス過去3年間の平均的な昇給実績(昇給率・昇給額)全社の平均残業時間と有給取得率の実績値 |
これらの質問に対して、「入社してから適性を見て判断します」「本人の頑張り次第です」といった曖昧な回答しか返ってこない場合は注意が必要です。
エンジニア一人ひとりのキャリアに真摯に向き合っている企業であれば、これらの質問に対して明確で納得のいく説明ができるはずです。
見極め(3)教育制度と案件選択の自由度
エンジニアが長期的に成長し、市場価値を高めていける企業かどうかを判断するためには、教育制度の充実度と、キャリアパスにおける本人の意思を尊重する仕組み、すなわち案件選択の自由度を確認することが極めて重要です。
優良企業は、エンジニアを単なる労働力としてではなく、共に成長するパートナーとして捉え、そのための投資を惜しみません。
まず注目すべきは、教育・研修制度です。
入社時の基礎研修はもちろんのこと、その後も継続的にスキルアップを支援する仕組みが整っているかを確認しましょう。
例えば、定期的な技術勉強会の開催、資格取得支援制度(受験費用補助や報奨金)、技術書の購入補助、外部研修への参加支援などが挙げられます。
「OJTで現場任せに覚えさせる」という一辺倒な姿勢ではなく、体系的な教育プログラムを用意している企業は、エンジニアの成長を真剣に考えていると評価できます。
次に、案件選択の自由度も重要な判断基準です。
エンジニアのキャリアプランを定期的にヒアリングする面談の機会が設けられているか、スキルマップなどを用いて目標設定をサポートする仕組みがあるか、そして最も重要な点として、次の案件を決定する際に本人の希望が尊重されるプロセスが明確になっているかを確認する必要があります。
「営業担当者が最適な案件を選びます」という説明だけでなく、エンジニアが複数の選択肢の中から自ら案件を選べる仕組みや、希望しない案件を断る権利があるかどうかまで踏み込んで質問することが、キャリアの主導権を自分で握るために不可欠です。
ITアウトソーシング以外の転職先

もしITアウトソーシングの働き方が自分には合わないと感じたとしても、悲観する必要は全くありません。
IT業界には、あなたのスキルと経験を活かせる多様なキャリアパスが存在し、それぞれに異なる魅力とやりがいがあります。
- 自社開発エンジニア
- 社内SE・情報システム部
- SIer・受託開発会社
- 非IT企業のDX部門
選択肢(1)自社開発エンジニア
自社のWebサービスやソフトウェア、アプリケーションなどのプロダクトを企画・開発・運用するのが、自社開発エンジニアの仕事です。
技術力を追求し、プロダクトの成長に直接貢献するやりがいを求める人に最適なキャリアパスと考えられます。
最大の魅力は、サービスの企画といった最上流の段階から関われる点です。
ユーザーからのフィードバックを直接受け取り、それを基に改善を重ねていくサイクルは、大きな手応えと達成感をもたらします。
また、多くの自社開発企業、特にWeb系の企業では、最新の技術やフレームワークを積極的に採用する文化があり、技術者としての市場価値を飛躍的に高めることが可能です。
年収の目安は450万円から650万円程度で、スキルや実績次第ではそれ以上も十分に狙えます。
ただし、求められるスキルレベルは高く、特に中途採用では1年以上の実務経験に加え、自身の技術力を証明するGitHubポートフォリオの提出が求められることが一般的です。
また、ベンチャー企業の場合は、一人ひとりの裁量が大きい反面、業務負荷が高くなる傾向もあります。
技術でプロダクトを良くしていくことに情熱を注げる人にとって、非常に魅力的な選択肢です。
選択肢(2)社内SE・情報システム部
社内SEは、事業会社の情報システム部門に所属し、社内のIT環境の整備や業務システムの管理・運用を担う職種です。
ワークライフバランスを重視し、安定した環境で腰を据えて働きたいと考えるエンジニアから高い人気を誇ります。
主な業務は、社員からの問い合わせに対応するヘルプデスク、PCやネットワークなどのIT資産管理、基幹システムや業務アプリケーションの企画・導入・運用・保守など多岐にわたります。
ユーザーが同じ会社の社員であるため、感謝の言葉を直接聞く機会が多く、自分の仕事が会社の業務効率化に貢献していることを実感しやすいのが魅力です。
残業が少なく、休日もカレンダー通りに取得しやすい企業が多いため、プライベートとの両立を図りやすいでしょう。
年収の目安は400万円から600万円程度ですが、大手企業の社内SEであれば700万円以上も期待できます。
一方で、企業によっては開発業務が少なく、外部ベンダーの管理や社内調整といった業務が中心になることもあります。
また、最先端の技術に触れる機会は自社開発企業に比べて少ない傾向があります。
ITの力で自社のビジネスを支える縁の下の力持ちとして貢献したい人に適したキャリアです。
選択肢(3)SIer・受託開発会社
SIerは、顧客となる企業からシステム開発や運用を請け負う企業です。
ITアウトソーシングよりも上流の工程からプロジェクトに携わり、高年収を目指したいと考える人にとって、最も現実的で有力な選択肢となります。
事実、情報通信業の平均年収は全産業の平均年収を大きく上回る水準にあり、SIerはその中でも比較的高待遇な企業が多いのが特徴です。
SIerには、以下のように、様々な種類があります。
- 独立系:親会社を持たない
- メーカー系:コンピュータメーカーを母体
- 通信系:通信会社を母体
- コンサル系:ITコンサルティングを主軸
| SIerの種類 | 特徴 | 年収の傾向 |
| 独立系 | 商流が浅く、幅広い業界の案件に関われる | 400万円~550万円 |
| メーカー系 通信系 | 大規模な社会インフラ案件が多く、安定性が高い | 600万円~800万円 |
| コンサル系 | 最上流の戦略立案から関われ、若手でも高年収 | 20代で1000万円も可能 |
最大のメリットは、要件定義や設計といった上流工程の経験を積みやすい点です。
顧客のビジネス課題をヒアリングし、それを解決するためのシステムを設計するスキルは、エンジニアとしての市場価値を大きく高めます。
プロジェクトマネジメントへの道もあり、キャリアアップの選択肢が豊富です。
ただし、顧客の要求や納期に厳しく縛られるため、プレッシャーが大きい側面もあります。
ITアウトソーシングで培った基礎を活かし、より大規模で責任のある仕事に挑戦したい人に最適なフィールドです。
選択肢(4)非IT企業のDX部門
近年、製造業や金融、小売といった非IT企業が、自社のビジネスモデルを変革するために設置しているのがDX推進部門です。
これは、従来のIT部門とは異なり、より経営に近い立場で、データ活用やAI導入、業務プロセスのデジタル化などを主導する役割を担います。
成長分野の最前線で、事業の根幹に関わるダイナミックな仕事ができる点が最大の魅力です。
ITアウトソーシングで得た様々な業界の知見を活かし、特定の事業会社の課題解決に深くコミットすることができます。
年収水準も高く、500万円から800万円程度が中心となり、管理職クラスでは1000万円を超えることも珍しくありません。
ただし、このキャリアパスには注意点も存在します。
DX推進という名目で採用されたにもかかわらず、実際には既存システムの保守運用や、社員のITサポートといった従来の情報システム部と同様の業務に配属されるケースがあるのです。
これは、社内にDXへの理解が浸透していなかったり、明確な戦略がなかったりする場合に起こりがちです。
この選択肢で成功するためには、技術力はもちろん、事業内容への深い理解と、社内の抵抗を乗り越えてでも変革を推進する強い意志が求められます。
面接の段階で、具体的なミッションや権限範囲を詳細に確認することが不可欠です。
ITアウトソーシングから転職を成功させる方法

ITアウトソーシングからのキャリアチェンジは、正しい準備と計画的な活動によって十分に実現可能です。
ここでは、あなたの経験を最大限に活かし、希望するキャリアへの転職を成功に導くための具体的な方法を「準備編」と「活動編」に分けて解説します。
- 実務スキルとポートフォリオの整理
- 職務経歴書とスキル棚卸し
- IT専門の転職エージェント活用
- 企業研究と面接対策
準備(1)実務スキルとポートフォリオの整理
現在の転職市場、特に自社開発企業やWeb系企業への転職において、自身の技術力を客観的に証明するポートフォリオの存在は、合否を左右するほど重要性を増しています。
ITアウトソーシングでの業務が保守運用やテスト中心で、開発経験が少ないと感じている方ほど、このポートフォリオ作成に力を入れるべきです。
ポートフォリオとは、自身のスキルや制作実績をまとめた作品集のことです。
たとえ業務経験がなくても、プライベートの時間を使ってアプリケーションを開発し、それを公開することで、学習意欲と技術力をアピールできます。
例えば、学習中のプログラミング言語を使って簡単なWebアプリケーションを制作し、AWSやHerokuといったクラウドサービス上にデプロイして公開するだけでも、採用担当者からの評価は大きく変わります。
重要なのは、単に作るだけでなく、そのプロセスや成果をきちんとドキュメント化し、伝える努力をすることです。
| ポートフォリオに 含めるべき要素 | 具体的な内容 |
| アプリケーション | 実際に動作し、URLでアクセスできる完成品 |
| ソースコード | GitHubなどのリポジトリで公開されたコード全体 |
| 技術スタック | 使用したプログラミング言語、フレームワーク、DB、インフラなど |
| コンセプト 工夫点 | なぜそのアプリを作ったのか、技術選定の理由、実装で工夫した点 |
| 技術ブログ | 開発過程で学んだことや、詰まった点を解決した記録(Qiitaなど) |
まずは小規模なものでも構いません。
実際に手を動かし、動くものを作り上げ、それを公開するという経験そのものが、あなたの技術力とポテンシャルを証明する何よりの証拠となるのです。
準備(2)職務経歴書とスキル棚卸し
ITアウトソーシングでの経験を、次のキャリアで高く評価される「価値」へと転換させるために不可欠なのが、徹底的なスキル棚卸しと、それを基にした戦略的な職務経歴書の作成です。
「テストを担当していました」「運用・保守をしていました」といった単なる業務の羅列では、あなたの本当の価値は伝わりません。
重要なのは、「どのような課題に対し、自身がどのように工夫・貢献し、その結果どのような成果が生まれたのか」を定量的な言葉で具体的に示すことです。
まずは、これまでの経験をプロジェクト単位で全て洗い出し、それぞれのプロジェクトで以下の内容を整理してみましょう。
- 「目的」
- 「自身の役割」
- 「使用技術」
- 「課題」
- 「行動・工夫」
- 「成果」
この作業を行うことで、アピールすべき強みが見えてきます。
例えば、職務経歴書は以下のように劇的に変わります。
| 改善前(Before) | 改善後(After) |
| 金融システムの結合テスト業務を3年間担当。 | 【プロジェクト】 〇〇銀行向け勘定系システム更改プロジェクト 【役割】結合テスト工程のリーダー 【課題】 従来の手動テストでは工数が逼迫し、ヒューマンエラーによる品質低下が懸念されていた。 【行動・工夫】 ・テストケース作成を効率化するため、Excelマクロを独学で習得し、作成時間を30%削減。 ・SQLを用いてテストデータを自動生成・検証する仕組みを構築し、不具合の検出率を向上。 【成果】 ・担当モジュールの本番リリース後の重大障害発生件数を、前年比で50%削減することに貢献した。 |
このように記述することで、単なる作業者ではなく、主体的に課題を解決できる人材であることを明確にアピールできます。
また、多様な現場を経験したITアウトソーシングならではの強みである「環境適応能力」や「顧客とのコミュニケーション能力」も、具体的なエピソードを交えて記述すると効果的です。
活動(1)IT専門の転職エージェント活用
転職活動を本格的にスタートするにあたり、IT業界に特化した転職エージェントの活用は、成功率を大きく高めるための有効な手段です。
転職エージェントは、個人ではアクセスできない非公開求人を多数保有しているだけでなく、業界の動向や企業の内情に精通したキャリアアドバイザーから専門的なサポートを受けられるという大きなメリットがあります。
ITアウトソーシングからのキャリアチェンジという特有の悩みを理解し、あなたの経歴をポジティブに評価してくれる企業を紹介してくれるでしょう。
利用する際は、複数のエージェントに登録し、それぞれの強みを見極めて併用することをおすすめします。
例えば、自社開発企業への転職に強いエージェント、社内SEの求人が豊富なエージェントなど、サービスごとに得意な領域が異なります。
重要なのは、エージェントを受け身で利用するのではなく、主体的に活用する姿勢です。
初回面談では、これまでの経歴だけでなく、将来どのようなエンジニアになりたいのかというキャリアの目標を具体的に伝えましょう。
そうすることで、アドバイザーはあなたに最適な求人を提案しやすくなります。
また、推薦状の内容を確認させてもらう、面接後のフィードバックを詳細にヒアリングするなど、積極的にコミュニケーションを取ることで、エージェントを自身の転職活動を成功させるための強力なパートナーとすることができるでしょう。
活動(2)企業研究と面接対策
希望する企業からの内定を勝ち取るための最終関門が、企業研究と面接対策です。
特に「なぜ他の会社ではなく、うちの会社なのですか?」という質問に対して、説得力のある回答ができるかどうかは、合否を大きく左右します。
そのためには、応募する企業一社一社について、深く掘り下げたリサーチが不可欠です。
企業研究は、以下の3つの軸で進めると効果的です。
| 研究の軸 | 具体的なアクション |
| 事業理解 | 公式サイトやIR情報でビジネスモデルや今後の事業戦略を把握する。 |
| 技術理解 | 技術ブログ、GitHub、採用ページで技術スタックや開発文化を調査する。 |
| カルチャー理解 | Wantedlyや社員インタビュー記事で、どのような人が働いているかを知る。 |
企業研究は、1社あたり最低でも2〜3時間以上かけるつもりで臨みましょう。
その上で、企業の課題と自身の経験・スキルを結びつけ、「自分ならこのように貢献できる」という一貫したストーリーを構築することが面接対策の核となります。
例えば、自社開発企業を受けるのであれば、実際にその企業のプロダクトを使ってみて、「ユーザーとして感じたこの課題を、私の〇〇という経験を活かしてこのように改善できると考えます」と具体的な提案ができれば、他の候補者と大きく差をつけることができます。
ITアウトソーシングでの経験は、決してマイナスではありません。
多様な環境で培った適応力や課題解決能力を、あなたの言葉で、志望企業に貢献できる価値として語ることが重要です。
まとめ
ITアウトソーシングが「やめとけ」と言われる背景には、年収の伸び悩みや配属ガチャによるスキル固定化といった構造的な課題があります。
将来に不安を感じるのは当然です。
しかし、全ての企業が悪いわけではなく、優良企業を見極める目を持つことが重要です。
また、現状から抜け出したいなら、自社開発・社内SE・SIerなど多様なキャリアパスが存在します。
まずはご自身のスキルを棚卸しし、長期的な視点でキャリアを設計しましょう。
希望のキャリアへ転職を成功させるため、専門知識を持つ転職エージェントに相談するのも有効な手段です。
ITアウトソーシングの「やめとけ」という言葉に惑わされず、仕組みを理解し、戦略的にキャリアを選ぶことが成功の鍵です。
この記事が、あなたが納得できる未来を選ぶための第一歩となれば幸いです。
\ 約90%が満足と回答した転職支援 /
非公開求人多数・詳細を確認




