SESで人生終了と検索してしまったあなたは、今まさに「このまま客先常駐を続けていいのか」と不安を抱えているのではないでしょうか。
多重下請け構造の中で案件ガチャに翻弄され、待機中の減給に怯え、スキルアップの機会も得られないまま時間だけが過ぎていく。
正当な評価も得られず、働き方を選ぶこともできない。
そんな状況から本気で抜け出したいと思いながらも、自分の市場価値に自信が持てず、転職活動の一歩が踏み出せずにいるかもしれません。
しかし安心してください。
この記事では、SESが「人生終了」と言われてしまう理由や、メリット・デメリット、さらに同じ悩みから脱出した人たちの体験談(モデルケース)などをわかりやすく整理して解説します。
今の環境で消耗し続けるのか、それとも行動を起こすのか、その選択はあなた次第です。
\ 転職者の約8割が年収アップに成功 /
高単価案件を今すぐチェック(無料)TOPICS
結論「SES=人生終了」は本当?
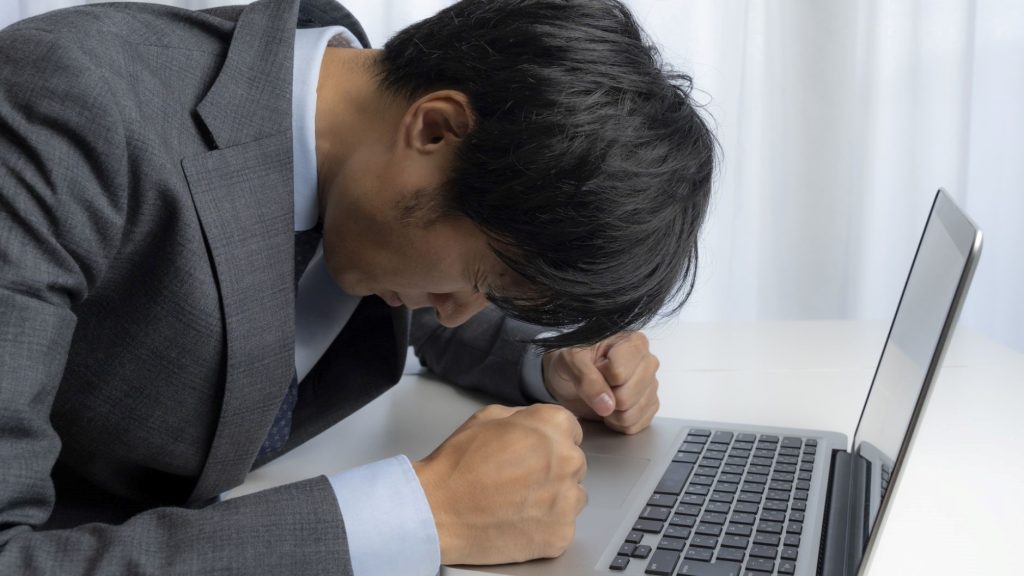
「SES=人生終了」という言葉に、自身のキャリアへの強い不安を感じているのではないでしょうか。
この章では、その言葉の真偽を明らかにし、あなたが自身の状況を客観的に判断するための具体的な基準を解説します。
- SESで「人生終了」になりやすい条件と自己診断
- 「人生終了」に当てはまらないケースとは
SESで「人生終了」になりやすい条件と自己診断
SESエンジニアとして働く環境がキャリアの停滞、すなわち「人生終了」状態を招くかどうかは、特定の条件が揃っているか否かで決まります。
もしあなたの職場が複数の危険な特徴に当てはまるなら、市場価値が下落するリスクが非常に高いと考えられます。
特に、多重下請け構造の下層に位置する企業では、エンジニアの成長機会が奪われ、正当な評価や報酬を得られない状況が生まれやすいでしょう。
例えば、客先への請求単価が月額70万円であるにも関わらず、エンジニアの給与が年収300万円台に留まるケースも存在します。
これは、自身の働きが生み出す価値の大部分が、所属企業や上位の会社に吸収されてしまっている証拠です。
さらに、会社の都合で配属先が一方的に決まる「案件ガチャ」の状態では、テストや運用保守といった下流工程に長期間固定される恐れがあります。
その結果、開発経験を積めないまま時間だけが過ぎ、年齢を重ねるごとに転職市場での選択肢が狭まってしまうのです。
まずは、以下の5つの項目であなたの現状を診断し、リスクレベルを客観的に把握することが重要です。
| 診断項目 | 内容 |
| 1. 案件の決定プロセス | 配属前に案件内容の十分な説明がなく、エンジニア自身の同意なしに一方的な配属が常態化している。 |
| 2. 給与の透明性 | 客先への請求単価や給与への還元率が一切開示されておらず、給与額の根拠が全くの不透明である。 |
| 3. 収入の安定性 | プロジェクト間の待機期間が発生した際、給与が80%未満に減額される規定があるか、実際に減額された経験がある。 |
| 4. 評価制度 | 所属企業の担当者との面談が年に1回未満であり、評価基準や昇給・昇格の条件が明文化されていない。 |
| 5. 業務内容 | 直近2年以上、主な業務がテストや運用保守であり、設計やプログラミングといった開発工程の経験をほとんど積めていない。 |
上記の項目に3つ以上当てはまる場合、あなたのキャリアは停滞するリスクが非常に高い状態です。
もし5つすべてに該当するなら、それは極めて危険な兆候であり、早急に環境を変えるための行動を起こすことを強く推奨します。
「人生終了」に当てはまらないケースとは
すべてのSES企業がキャリアの停滞を招くわけではありません。
エンジニアの成長と正当な評価を重視する優良なSES企業も存在し、そのような環境では市場価値を着実に高めることが可能です。
重要なのは「SESという働き方」を問題視するのではなく、「どのような条件の企業で働くか」を見極めることです。
近年、深刻なエンジニア不足を背景として、優秀な人材を確保するために、労働条件の透明性を高め、教育に投資する企業が増加傾向にあります。
例えば、還元率75%以上を公言したり、待機期間中の給与を100%保証したりする企業がそれにあたります。
こうした企業は、エンジニアが自身の市場価値を正しく認識し、納得感を持って働ける環境を提供していると言えるでしょう。
また、エンジニア本人のキャリアプランを尊重し、配属前に必ず本人の同意を得るプロセスを設けている企業も増えています。
これにより、技術的なミスマッチやキャリアパスの分断を防ぎ、専門性を深めていくことが可能となります。
「人生終了」を招く企業と、キャリアアップを実現できる優良企業には、以下のような明確な違いがあります。
この基準を理解し、現在の職場や転職候補の企業を冷静に評価すれば、あなたの未来を大きく左右するでしょう。
| 比較項目 | 危険なSES企業の特徴 | 優良なSES企業の特徴 |
| 給与の透明性 | 単価・還元率が非開示で、給与の根拠が不透明。 | 月次などで単価と還元率を開示し、昇給の根拠が明確。 |
| 案件選択の自由度 | 会社の都合で一方的に配属され、本人の希望はほとんど考慮されない。 | 配属前に案件内容を詳細に説明し、本人が納得した上で決定する同意プロセスがある。 |
| 収入の安定性 | 待機期間中は給与が大幅に減額される(80%未満など)。 | 待機期間中も給与が100%保証され、収入が途切れない。 |
| 評価の公平性 | 評価面談の頻度が低く、基準も曖昧。 現場での貢献が評価に反映されにくい。 | 月1回以上の面談があり、評価制度が明確。 現場での成果が昇給・昇格に直結する仕組みがある。 |
| 成長機会 | 下流工程の案件が多く、開発経験を積む機会が乏しい。 | 要件定義から関われる開発案件が豊富で、継続的な学習を支援する制度(資格取得支援など)が充実している。 |
このように、SESという枠組みの中でも、エンジニアのキャリアに対する考え方は企業によって大きく異なります。
もし現在の環境が危険な特徴に多く当てはまるとしても、業界全体を悲観する必要はありません。
まずは正しい知識を身につけ、あなた自身の価値を正当に評価してくれる企業を見極めることが重要です。
「SES=人生終了」と言われる主な理由

あなたが感じている将来への不安や現在の待遇への不満は、個人的なスキル不足だけが原因ではないかもしれません。
この章では、なぜ「SES=人生終了」という言葉がネット上で広まっているのか、その構造的な理由を解説します。
- 多重下請けによる低単価・低賃金
- 案件ガチャでスキルが積み上がらない
- 待機期間中の給与減額リスク
- 客先常駐で評価が伝わりにくい
- 年齢を重ねても職域が広がらない
多重下請けによる低単価・低賃金
SES業界における低賃金の最大の理由は、多重下請け構造による中間マージンの発生です。
これは、元請けのIT企業が受注した大規模なプロジェクトを、2次請け、3次請けと複数の下位企業へ再委託していく業界の慣習を指します。
問題なのは、商流の各段階でそれぞれの企業が利益としてマージンを差し引くため、階層が下がるほどエンジニアの働きに対する単価が大幅に減少してしまう点です。
例えば、元請け企業が顧客から月額100万円で受注した案件を考えてみましょう。
この案件が2次請けに渡る際に15%のマージンが引かれて85万円に、さらに3次請けに渡る際に15%が引かれて約72万円になります。
最終的にあなたが所属するSES企業が、そこから管理費や利益として30%〜40%のマージンを差し引くことも珍しくありません。
その結果、元は100万円だった価値が、あなたの給与の元となる金額としては40万円台まで下落してしまうのです。
この構造がある限り、たとえ現場でどれだけ高いパフォーマンスを発揮しても、その成果が正当な報酬としてあなたに還元されることは極めて困難となります。
特に、単価や還元率を公開していない企業では、自分が不当に低い報酬で働かされている事実に気づくことすらできません。
案件ガチャでスキルが積み上がらない
多くのSESエンジニアがキャリア形成に苦しむ原因として、本人の希望や適性を無視して配属先が決められる、通称「案件ガチャ」が挙げられます。
この問題の背景には、エンジニアの稼働率を最大化することで利益を上げるというSES企業のビジネスモデルが存在します。
企業にとって、エンジニアが次の案件を待っている「待機期間」は、売上を生まない単なるコストでしかありません。
そのため、エンジニア本人のキャリアプランやスキルアップへの意欲よりも、会社が保有している「今すぐ参画できる案件」の都合が優先されがちになるのです。
結果として、あるプロジェクトではJavaを用いたサーバーサイド開発をしていたにも関わらず、次のプロジェクトでは全く系統の異なるインフラの運用保守を担当させられる、といった事態が発生します。
このような働き方を繰り返していると、一つの技術を深く追求する時間がなく、どの分野においても中途半端なスキルしか身につきません。
転職市場では、特定の技術領域における一貫した経験や専門性が高く評価される傾向が強いです。
そのため、多様な案件を経験したという経歴が、逆に「専門性がない」と見なされ、キャリアアップの足かせとなってしまうリスクがあります。
待機期間中の給与減額リスク
SESという働き方には、プロジェクトの終了や突然の契約打ち切りによって、次の配属先が決まるまでの待機期間が発生するリスクが常に伴います。
この期間中の収入が不安定であることが、エンジニアの生活とキャリアプランに大きな影を落とす一つの理由です。
多くのSES企業では、この待機期間中の給与を通常の80%、70%、ひどい場合には60%程度まで減額する就業規則を定めています。
法律上、会社都合による休業の場合は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務がありますが、生活水準を維持するには十分な金額とはいえません。
企業側が給与を減額する理由は、エンジニアが客先で稼働していない時間は、会社にとって一切の利益を生み出さないためです。
この収入減は、単に経済的な不安をもたらすだけではありません。
「早く次の案件を決めなければ生活が苦しくなる」という精神的な焦りが、キャリアにとって不利益な判断を招くことになります。
例えば、本来であれば避けたいスキルアップにつながらない下流工程の案件や、労働環境の悪いプロジェクトであっても、収入を確保するために受け入れざるを得なくなるのです。
この悪循環に陥ると、自身の市場価値をさらに下げる結果となり、ますます不利な状況から抜け出せなくなります。
客先常駐で評価が伝わりにくい
客先常駐という勤務形態は、エンジニアの成果が所属企業に正しく伝わらず、公平な評価を受けにくいという構造的な問題を抱えています。
日々の業務における指示や管理は配属先の社員から受けるため、所属企業の上司や評価者があなたの働きぶりを直接目にすることはありません。
所属企業の担当者があなたの状況を把握する機会は、月に一度の面談や、あなたが提出する業務報告書に限られるのが実情です。
そのため、評価の主な判断材料は、配属先の担当者からの又聞きや形式的なフィードバックに依存せざるを得ません。
しかし、配属先の担当者にとって、外部のエンジニア一人ひとりの詳細な評価を作成する義務もインセンティブもありません。
結果として、「問題なく業務を遂行しています」といった当たり障りのないコメントで終始することが多く、あなたが現場で達成した具体的な成果や、課題解決のために行った工夫などが評価に反映されにくいのです。
このような状況では、個人の貢献度に応じた昇給や昇格は期待しにくく、評価が横並びになります。
どれだけ努力をしても正当に評価されないという経験は、仕事へのモチベーションを著しく低下させ、キャリアアップへの意欲を削いでしまう大きな要因です。
年齢を重ねても職域が広がらない
SESエンジニアとして働く上で、長期的なキャリアを脅かす深刻なリスクが、年齢を重ねても担当業務の範囲が広がらないという問題です。
一般的なキャリアパスでは、20代でプログラミングやテストといった下流工程の経験を積み、30代にかけて設計などの上流工程や、チームリーダーといったマネジメントの役割へと移行していきます。
しかし、SESの現場では、このようなキャリアアップが実現しにくい構造が存在します。
その理由は、プロジェクトにおける役割分担が、元請け企業と下請け企業の間で明確に区切られているためです。
要件定義や設計といったプロジェクトの根幹に関わる上流工程は、元請けや顧客企業の正社員が担当することがほとんどです。
一方で、SESエンジニアは、特定の機能の実装やテストといった、限定された役割を担うための「リソース」として扱われる傾向が強くなります。
そのため、何年も同じ企業で働き続けても、任される業務は下流工程のままというケースが少なくありません。
その結果、30代になっても実装やテストの経験しかなく、同年代のエンジニアが持つべき設計スキルやマネジメント経験が欠落しているという事態に陥ります。
転職市場において、このスキルと年齢のミスマッチは致命的です。
企業は、年齢相応のスキルや経験を求めるため、応募できる求人の選択肢は大幅に狭まり、キャリアの行き詰まり、すなわち「人生終了」状態を招くことになります。
SESのデメリット

SESという働き方には、業界の構造から生まれる特有のデメリットが存在します。
これらのデメリットを正しく理解することは、あなたが自身のキャリアを守り、将来のリスクを回避するために不可欠です。
- 単価・還元率・評価が不透明になりやすい
- 配属主導でキャリアの一貫性を失いやすい
- 契約打ち切り・待機の収入不安定性
単価・還元率・評価が不透明になりやすい
SESエンジニアが直面する最大のデメリットの一つが、自身の待遇の根拠となる情報がブラックボックス化されやすいことです。
以下の3つの要素が不透明な企業が多く、これがエンジニアのキャリア形成を著しく阻害します。
- 客先への請求単価
- 給与への還元率
- 人事評価の基準
単価と還元率が非公開である場合、あなたは自分の働きが市場でどれだけの価値を生んでいるのかを知ることができません。
そのため、現在の給与が適正な水準にあるのかを判断する客観的な材料がなく、昇給を求める際の具体的な交渉も困難になります。
これは、自身の価値を正当に主張する権利を事実上放棄させられている状態です。
さらに、客先常駐という働き方の特性上、所属企業による人事評価の基準も曖昧になります。
明確な評価基準がなければ、あなたは「何を達成すれば評価され、昇給や昇格につながるのか」というキャリアアップの道筋を描くことができません。
目標が不明確なままでは、スキルアップへのモチベーションを維持することも難しくなります。
これら3つの不透明性は、エンジニアから健全な労働意欲と成長機会を奪う、非常に根深い問題なのです。
配属主導でキャリアの一貫性を失いやすい
SESでは、配属先をエンジニア自身のキャリアプランに基づいてではなく、企業の利益都合によって決定されるケースが少なくありません。
この企業主導の配属が、専門性を高めたいエンジニアにとって大きなデメリットとなります。
SES企業の収益はエンジニアの稼働率に直結するため、待機期間をなくすことが最優先課題です。
その結果、あなたの「特定の技術を極めたい」という希望よりも、会社が抱える「すぐに参画できる案件」の都合が優先されてしまうのです。
これにより、プロジェクトごとに使用する言語や担当する領域が変わり、一貫したスキルを積み上げることが難しくなります。
例えば、サーバーサイドの専門家を目指しているにも関わらず、インフラ運用やフロントエンドの保守案件にアサインされるといった事態が起こり得ます。
こうした経験は、一見すると対応範囲が広いように見えますが、転職市場では「器用貧乏」と見なされ、市場価値を高める上では不利に働くことが多いでしょう。
なぜなら、多くの企業は、広く浅い知識を持つ人材よりも、特定の分野で深い専門性を持つ即戦力人材を求めるからです。
キャリアの軸が定まらないままでは、年次を重ねても「これが私の専門です」と断言できる強みが形成されず、長期的なキャリア構築において大きなハンディキャップを背負うことになります。
契約打ち切り・待機の収入不安定性
SES契約はプロジェクト単位での有期契約が基本であるため、常に契約打ち切りやプロジェクト終了のリスクと隣り合わせです。
それに伴う待機期間中の収入減は、エンジニアの生活とキャリアに深刻な影響を及ぼすデメリットです。
多くのSES企業では、待機期間中の給与を通常時の6割から8割程度に減額する規定を設けています。
この収入の不安定さは、単に経済的な問題に留まりません。
むしろ、それがもたらす精神的な焦りが、キャリアプランを狂わせる二次的な被害を生むことの方が問題は深刻です。
| 不安定性がもたらす影響 | 具体的なデメリット |
| 経済的な不安 | 毎月の収入が変動するため、住宅ローンや子育て費用といった長期的なライフプランを立てにくい。 貯蓄を切り崩す生活が続くと、将来への不安が増大する。 |
| 精神的な焦り | 「早く次の現場を決めなければ」というプレッシャーから、冷静な判断ができなくなる。 |
| キャリア選択の制限 | 収入を確保することを最優先するあまり、スキルアップにつながらない案件や、希望しない技術領域の案件でも受け入れざるを得なくなる。 これがキャリア停滞の悪循環を生み出す。 |
このように、収入の不安定性は、エンジニアから「より良い案件を選ぶ」という当然の権利を奪い、不本意なキャリアを歩ませる原因となり得ます。
安定した生活基盤の上で、腰を据えてスキルアップに取り組むことが難しいという点は、SESという働き方が持つデメリットの一つです。
SESのメリット

SESには多くの課題がある一方で、キャリアの特定の段階においては有効に活用できるメリットも存在します。
この章では、SESという働き方が持つメリットと、それを最大限に活かすための視点を解説します。
- 未経験〜若手でも参画の間口が広い
- 多様な現場で基礎スキルを横断習得できる
- 実績次第で上位案件・条件改善の余地がある
未経験〜若手でも参画の間口が広い
SESのメリットは、実務経験が乏しい未経験者や若手のエンジニアにとって、IT業界への扉が広く開かれている点です。
人気の自社開発企業や受託開発企業の多くは、即戦力となる経験豊富なエンジニアを求める傾向が強く、未経験者が採用されるハードルは非常に高いのが現実です。
一方で、SES企業はテストや運用保守、ヘルプデスクといった、比較的専門的な開発スキルを必要としない案件も多数扱っています。
そのため、採用の門戸が広く、まずはIT業界に入って実務経験を積みたいと考える人材にとって、貴重な受け皿となっているのです。
これは、エンジニアを客先に常駐させて利益を得るというビジネスモデル上、常に一定数の人材を確保する必要があるためです。
多くのSES企業では、プログラミング未経験者を採用し、数ヶ月間の研修を受けさせた後に現場へ配属する、という育成プログラムが確立されています。
もちろん、研修の質や配属される案件の内容には企業差がありますが、実務経験ゼロの状態からキャリアをスタートさせるなら、SESは非常に有効な選択肢です。
多様な現場で基礎スキルを横断習得できる
SESは、短期間で多種多様なプロジェクトや業界を経験できます。
これは、特定のプロダクトやサービスに長期間関わる自社開発企業では得難い経験であり、特にキャリアの方向性が定まっていない若手エンジニアにとっては、自身の適性を見極める絶好の機会です。
例えば、あるプロジェクトでは金融システムの開発に携わり、次のプロジェクトではECサイトの構築に関わる、といった経験を積むことが可能です。
これにより、特定のプログラミング言語のスキルだけでなく、それぞれの業界特有の業務知識や専門用語(ドメイン知識)を幅広く習得できます。
また、プロジェクトごとに開発環境やチームの文化も異なります。
| 経験できる環境の多様性 | 具体的な内容 |
| 開発手法 | 大規模プロジェクトで用いられることが多いウォーターフォール開発と、Webサービス開発で主流のアジャイル開発の両方を経験できる可能性がある。 |
| 企業文化 | 大企業の厳格なルールに基づいた開発プロセスと、スタートアップ企業のスピード感を重視した開発文化の違いを肌で感じることができる。 |
| 技術スタック | JavaやC#といったエンタープライズ向けの技術から、PHPやRuby、PythonといったWeb系の技術まで、案件に応じて様々な技術に触れる機会がある。 |
これらの多様な経験は、エンジニアとしての視野を広げ、技術的な引き出しを増やす上で非常に有益です。
将来、自分がどの領域を専門にしていきたいのかを考える上で、判断材料が豊富になるという点は大きなメリットです。
実績次第で上位案件・条件改善の余地がある
SESは、現場での実績や評価が、次のキャリアステップに直結しやすいというメリットがあります。
客先常駐という働き方は、あなたのパフォーマンスが顧客の目に直接触れます。
そのため、配属先で高い評価を得て、「この人にならもっと重要な仕事を任せたい」「次のプロジェクトもぜひお願いしたい」という信頼を勝ち取ることができれば、それがキャリアアップの強力な推進力となるのです。
SES企業の営業担当にとっても、現場から高評価を得ているエンジニアは、より単価の高い、条件の良い案件を提案しやすくなります。
顧客からの指名があれば、単価交渉も有利に進められるため、企業とエンジニア双方にとって利益があるからです。
実際に、最初はテスト業務を担当していたエンジニアが、その正確性と効率性を評価され、次の契約更新時にプログラミングを担当する開発フェーズにステップアップする、というケースは珍しくありません。
さらに、そこで実績を積めば、基本設計や要件定義といった、より上流の工程を任される道も開けてきます。
単価の上昇は、高還元率を掲げる優良なSES企業であれば、あなたの給与に直接反映されます。
つまり、自社内での昇進を待つだけでなく、現場での実力と信頼を武器に、自らの手で待遇を改善していける可能性があるという点は、SESならではのメリットでしょう。
SESにおける典型的なキャリアパスのモデルケース

ここでは、SESエンジニアが陥るキャリアパスを、具体的なモデルケースとして紹介します。
これまで解説してきたリスクが、一個人のキャリアにどのような影響を与えるのかを理解することで、あなたが今後取るべき行動がより明確になるでしょう。
- 失敗モデル1:育成を軽視され、単純作業に固定されるケース
- 失敗モデル2:スキルと案件のミスマッチで疲弊するケース
- 失敗モデル3:キャリアに一貫性がなく、市場価値が停滞するケース
- 成功モデル:SESでの経験を糧にキャリアアップを実現するケース
失敗モデル1:育成を軽視され、単純作業に固定されるケース
IT業界での活躍を夢見て、未経験からSES企業に入社したAさんのモデルケースです。
入社前、Aさんは「充実した研修制度で一から学べる」という説明に魅力を感じていました。
しかし、実際の研修はわずか数週間で、プログラミングの基礎に触れる程度で終了します。
十分な知識がないまま、Aさんはテスト業務を行うプロジェクトに配属されました。
最初は「これも経験だ」と考えていましたが、契約が更新されても業務内容は変わらず、Excelでのテスト項目書の作成と実行を繰り返す毎日が続きます。
開発に携わりたいと所属企業の営業担当に相談しても、「まずは今の現場で信頼を得ることが重要だ」とかわされるばかりです。
数年が経過し、Aさんの主なスキルは「テスト仕様書の作成」と「手動テストの実行」のみとなりました。
その間、所属企業からのフォローやキャリア面談はほとんどなく、Aさんは自分が会社の利益を生むための「使い捨ての駒」として扱われていると感じるようになります。
いざ転職を考えても、職務経歴書に書ける開発経験がなく、同年代のエンジニアとのスキル差に愕然とすることになるのです。
失敗モデル2:スキルと案件のミスマッチで疲弊するケース
実務経験1年のBさんは、さらなるスキルアップを目指して開発案件への参画を希望していました。
ある日、営業担当から「Webアプリケーションの開発案件です」と紹介され、Bさんはそれを承諾します。
しかし、実際にプロジェクトに参加してみると、求められるスキルレベルはBさんが持つ経験をはるかに超えていました。
このミスマッチの背景には、案件を獲得したい営業担当が、Bさんのスキルシートを実態よりも良く見せて提案していたという事実があります。
契約が始まってしまった以上、Bさんは後戻りできません。
周囲の期待に応えようと必死に業務に取り組みますが、基礎知識が不足しているため作業は遅々として進まず、連日のように残業が続きます。
平日は業務に追われ、休日は疲労回復に充てるだけで精一杯なため、スキル不足を補うための学習時間も確保できません。
Bさんは次第に心身ともに消耗し、仕事への自信を完全に失ってしまいます。
このケースの恐ろしい点は、スキルが向上しないまま時間と自信だけが失われ、エンジニアとしてのキャリアそのものに絶望してしまうリスクがあることです。
失敗モデル3:キャリアに一貫性がなく、市場価値が停滞するケース
経験5年目のCさんは、これまで複数のプロジェクトを経験してきました。
Cさんの職務経歴書には、Java、PHP、Pythonといった複数の言語や、Web開発、インフラ構築、データ分析基盤の運用など、多岐にわたる経験が記載されています。
20代の頃は、様々な技術に触れられることをポジティブに捉えていました。
しかし、30歳を目前にして転職活動を始めたCさんは、厳しい現実に直面します。
面接官から「あなたの専門分野は何ですか?」と問われた際に、明確に答えることができないのです。
Cさんの経験は、どれも1年未満の短期的なものが多く、「広く浅い」と評価されてしまいました。
企業が中堅エンジニアに求めるのは、特定の技術領域における深い知見と、問題を解決に導いた実績です。
Cさんのように、企業の都合で一貫性のないキャリアを歩んできたエンジニアは、転職市場では「専門性がない人材」と見なされ、年齢相応の評価を得ることが難しくなります。
キャリアの軸が定まらないまま年次を重ねてしまうと、市場価値が上がらず、年収も停滞するという典型的な失敗モデルです。
成功モデル:SESでの経験を糧にキャリアアップを実現するケース
Dさんは、Cさんと同じく複数のプロジェクトを経験しましたが、その後のキャリアは大きく異なります。
Dさんは、企業主導の配属にキャリアを委ねることに早くから危機感を抱いていました。
そこで、Dさんは日々の業務と並行して、自分が専門にしたいと考えるサーバーサイド開発の技術領域の自己学習を継続します。
具体的には、学習した内容をまとめた技術ブログを運営し、オリジナルのWebアプリケーションを個人で開発して、そのソースコードをGitHubで公開しました。
これらの活動は、Dさんの「能動的な学習意欲」と「実践的な開発スキル」を客観的に証明する強力な材料となります。
転職活動の際、Dさんは職務経歴書において、一見バラバラに見えるSESでの経験を「多様な開発環境への適応力」や「様々な立場の人と円滑に業務を進めるコミュニケーション能力」という強みとして再定義しました。
その上で、ポートフォリオとして提示した個人開発の成果物を根拠に、サーバーサイド開発への強い熱意と専門性をアピールしたのです。
結果として、Dさんは自社でWebサービスを開発する企業への転職を成功させ、年収の大幅アップも実現しました。
このモデルは、SESでの経験を無駄にせず、主体的な行動によってキャリアを好転させられることを示しています。
人生終了になりやすいSES企業の特徴

あなたのキャリアを停滞させるリスクの高いSES企業には、いくつかの共通した特徴が見られます。
ここでは、入社前に必ず見極めるべき危険な兆候を具体的に解説しますので、企業選びの際の判断基準としてください。
- 未経験歓迎なのに研修がない
- 給与体系・還元率が不透明
- 経歴詐称を示唆・強要する
未経験歓迎なのに研修がない
「未経験者歓迎」という言葉を掲げながら、実質的なエンジニア育成体制を整えていない企業は極めて危険です。
このような企業は、エンジニアの長期的な成長に投資するのではなく、単なる労働力として短期的に消費することしか考えていません。
特徴的なのは、入社後の研修が数日から数週間程度の、ごく形式的なもので終わってしまう点です。
ビジネスマナーやIT業界の基礎知識にわずかに触れるだけで、実践的なプログラミングスキルを習得する機会がないまま、すぐに客先へ常駐させられます。
企業側にとって、エンジニアが研修を受けている期間は売上を生まない「コスト」でしかありません。
そのため、一日でも早く現場に送り込み、稼働させることを優先するのです。
結果として、スキルが不十分なエンジニアは、配属先で簡単なテストや運用保守といった、誰にでもできる単純作業しか任されません。
開発経験を積む機会がないまま時間だけが過ぎ、スキルレベルは入社時からほとんど変わらないという事態に陥ります。
これは、エンジニアを育成対象ではなく、利益を生むための「駒」としか見ていない企業体質の明確な現れです。
給与体系・還元率が不透明
自身の給与の根拠となる情報を意図的に隠蔽する企業は、エンジニアに適正な報酬を支払っていない可能性が非常に高いでしょう。
特に注意すべきなのは、以下の2つを一切開示しない企業です。
- 客先への請求単価
- 給与への還元率
あなたが客先で働いた対価として、顧客から所属企業へいくらの金額が支払われているのか。
そして、そのうちの何パーセントがあなたの給与として支払われているのか。
これらの情報は、あなたが自身の市場価値を正しく認識し、待遇に納得して働く上で不可欠なものです。
優良な企業はこれらの情報をオープンにし、透明性の高い制度をアピールします。
一方で、これらの情報を隠そうとする企業は、不当に高い中間マージンを設定し、エンジニアの成果を過度に搾取しているケースが後を絶ちません。
情報を非公開にすることで、エンジニアに交渉の材料を与えず、低い給与水準に甘んじさせようという意図が見え隠れします。
このような不誠実な企業では、あなたがどれだけ価値の高い仕事をしても、その成果が報酬に反映されることは期待できません。
経歴詐称を示唆・強要する
コンプライアンス意識が著しく欠如し、エンジニアに経歴の詐称を求める企業は、絶対に関わってはいけない最も悪質な存在です。
これは、自社の利益のためにエンジニアを犯罪行為に巻き込む、許されざる行為です。
具体的な手口としては、営業担当者が案件を獲得しやすくするために、以下のようにスキルシートの改ざんを指示してきます。
- 「実務経験1年を3年に見せかけましょう」
- 「この言語は使ったことがなくても、経験ありということにしてください」
これは単なる倫理的な問題に留まりません。
発覚した場合には詐欺罪に問われる可能性があり、あなた自身も共犯者としてキャリアに大きな傷がつくリスクを伴います。
また、仮に偽りの経歴で案件に参画できたとしても、そこで待っているのは苦難です。
現場では、あなたが持っているはずのスキルを前提に業務が割り振られます。
実力に見合わない高い要求に応えられず、パフォーマンスの低さから周囲の信頼を失い、精神的に追い詰められてしまうでしょう。
経歴詐称の強要は、エンジニアの尊厳とキャリアを破壊する行為であり、そのような要求をしてくる企業は、即座に関係を断つべきです。
まとめ
「SES=人生終了」という不安は、多重下請け構造や「案件ガチャ」によるスキル停滞、不透明な評価が原因です。
本記事では、こうした状況に陥る理由と、具体的な回避策を解説しました。
重要なのは、劣悪な環境のSESと優良なSESを見極めることです。
現状に当てはまるか診断し、もしリスクが高いならすぐに行動が必要です。
解説してきた内容を参考にし、専門の転職エージェントも活用しながら受託開発・自社開発など、キャリアを立て直す第一歩を踏み出しましょう。
\ 約90%が満足と回答した転職支援 /
非公開求人多数・詳細を確認




