転職活動中のエンジニアがつまずきやすいのが、「なぜ自分はインフラエンジニアを志望したのか」を明確に伝えることです。
単に「需要があるから」「安定しているから」という志望動機だけでは、採用担当者には響きません。
実際、多くの企業はあなたがインフラエンジニアとして「何をやりたいのか」「どう成長したいのか」を知りたいと考えています。
では、どうすればあなたらしさを伝えつつ、説得力のある志望動機を書けるのでしょうか?
今回は採用担当者の心を掴むポイントを具体的に解説します。
\ 転職者の約8割が年収アップに成功 /
TOPICS
インフラエンジニアの志望動機の基本構成と書き方

この章では、説得力のあるインフラエンジニアの志望動機を作成するための基本的な文章構成について紹介します。効果的な志望動機の構成には主に以下の内容があります。
- インフラエンジニアになりたい理由を明確に示す結論部分
- その結論に至った背景や経緯を説明する理由部分
- 自分の経験やスキルを示す具体的なエピソード部分
- 入社後のビジョンと熱意を伝えるまとめ部分
結論:なぜインフラエンジニアになりたいのか
志望動機の冒頭で「なぜインフラエンジニアになりたいのか」を明確に述べることは、読み手の関心を引きつけ、志望動機全体の方向性を示す重要な要素です。
採用担当者は多くの志望動機を読むため、最初の数行で興味を持てなければ残りの内容も流し読みされてしまう可能性があります。
結論を最初に示すことで、その後の理由や具体例が結論を裏付ける構造となり、論理的で理解しやすい文章になります。
具体的には「システムの土台を支え、企業活動を安定させるインフラエンジニアになりたいと考えています」や「技術革新の基盤となるITインフラの構築・運用に携わりたいと思い、インフラエンジニアを志望いたします」といった表現が効果的です。
結論は1-2文で簡潔に表現し、自分の価値観や目指す方向性が伝わる内容にしましょう。
抽象的な表現ではなく、インフラエンジニアの具体的な魅力や役割に言及することで、職種への理解度をアピールできます。
理由:結論に至った背景と経緯
結論に至った背景と経緯を詳しく説明することで、志望動機の説得力を高め、採用担当者に納得感を与えることができます。
単に「インフラエンジニアになりたい」と述べるだけでは、その動機の深さや本気度が伝わりません。
どのような体験や気づきがきっかけとなったのか、どんな価値観や考え方の変化があったのかを具体的に説明することで、志望動機に深みと信憑性を持たせることができます。
例えば、学生時代のシステム障害体験からインフラの重要性を実感した経緯や、前職での業務システム利用経験から安定したシステム基盤への関心が高まった過程などが挙げられます。
IT関連の学習を通じてインフラ技術の奥深さや社会的意義を理解した体験や、身近なサービス停止の体験からインフラエンジニアの社会的責任を感じた経緯も効果的です。
時系列で経緯を整理し、感情の変化や気づきのポイントを具体的に表現することで、ストーリーとしての魅力を高められます。
具体例:経験やスキルのエピソード
自分の経験やスキルを具体的なエピソードで示すことで、インフラエンジニアとしてのポテンシャルや適性を効果的にアピールできます。
抽象的なスキルの羅列では採用担当者に印象を残すことができないため、具体的なエピソードを通じて、どのような状況でどんな行動を取り、どのような結果を出したのかを示すことが重要です。
学習プロジェクトでのサーバー構築体験と、そこで学んだ技術的知識や、前職でのシステムトラブル対応経験と問題解決への取り組み姿勢などが具体例として挙げられます。
チームプロジェクトでのリーダーシップ発揮やコミュニケーション能力の実証、資格取得への継続的な取り組みと自己成長への意欲の表れも効果的です。
また、前職での品質管理経験と細かい作業への集中力や責任感の実例なども活用できます。
まとめ:入社後のビジョンと熱意
志望動機の最後に入社後のビジョンと熱意を示すことで、将来への展望と企業への貢献意識を伝え、採用担当者に強い印象を残すことができます。
採用担当者は「この人を採用したら、どのような価値を企業にもたらしてくれるか」「長期的に活躍してくれるか」を評価するため、入社後の具体的なビジョンと熱意を示すことが重要です。
短期的な技術習得目標とそれを通じた企業への貢献計画や、中長期的なキャリアビジョンと企業での成長への期待を具体的に示しましょう。
学び続ける姿勢と技術の進歩に対応していく決意、チームへの貢献意識と組織の一員としての責任感も重要な要素です。
企業の事業成長への貢献意欲と社会的使命への共感、技術を通じた価値創造への意欲とプロフェッショナルとしての成長目標も効果的に盛り込めます。
企業の事業内容や技術方向性を踏まえた現実的なビジョンを示し、期限や数値目標を含めることで具体性を高め、最後に熱意を込めた決意表明で締めくくることが大切です。
インフラエンジニアの志望動機を書く際のポイント
インフラエンジニアの志望動機を作るのが難しいという方は非常に多いでしょう。
ここでは、インフラエンジニアの志望動機を作る際のポイントについて以下の4点に注目して解説していきます。
- 自分のスキルや経験を整理し、得意分野や強みをアピールする
- インフラエンジニアになりたい理由や熱意を明確に示す
- その企業を選んだ理由、入社したい理由を具体的に書く
- 入社後にどのようなキャリアビジョンを描いているのかを書く
自分のスキルや経験を整理し、得意分野や強みをアピールする
これまでの経験とスキルを体系的に整理し、インフラエンジニアの業務にどう活かせるかを明確にすることで、採用担当者に具体的な価値提供をアピールできるようになります。
未経験者であっても、これまでの経験には必ずインフラエンジニアの業務に活かせる要素があるため、それらを整理して言語化することでポテンシャルの高さを示すことが可能です。
技術的経験としては、プログラミングやネットワーク設定、データベース操作などがあり、業務スキルではプロジェクト管理や品質管理、トラブル対応、顧客対応などが該当します。
また、論理的思考や継続学習、責任感、コミュニケーション能力といった個人的特性や、IT関連資格、技術書籍の読書、オンライン学習といった自己研鑽の取り組みも重要な要素です。
製造業での品質管理経験や、サービス業での顧客対応経験、営業での提案力なども、インフラエンジニアの業務と関連付けることができます。
その企業を選んだ理由、入社したい理由を具体的に書く
具体的かつ明確に示すことは非常に重要です。
これを明確にできていないと、面接の際などに「ウチである必要性がないのでは?」と言及されてしまう可能性もあります。
そのため、その企業の技術領域や得意分野、社風や働き方、社会的使命や事業内容、成長性や将来性、教育制度やキャリア支援制度などを詳しく調べ、その中から自分の価値観や目標と最も合致する点を見つけるようにしましょう。
例えば、クラウド技術に強い企業であれば「最新のクラウド技術を学べる環境」、地域密着型の企業であれば「地域社会への貢献」といった具体的な魅力を志望動機に盛り込むことで、企業研究をしっかり行った本気度を示すことができます。
また、可能であれば企業の製品やサービスを利用し、その経験や魅力を志望動機に織り込むことができると説得力が生まれます。
企業研究だけにとどまらず業界の研究も行って、業界におけるその企業の立ち位置なども交えて語ることができるとなおよいでしょう。
インフラエンジニアになりたい理由や熱意を明確に示す
IT関連のエンジニアだけに絞ってみても、データーベースエンジニアやネットワークエンジニア、セキュリティエンジニア、フルスタックエンジニアなど、たくさんの職種があります。
採用担当者が最も知りたいのは「なぜ数あるIT職種の中でインフラエンジニアを選んだのか」という点であり、この理由が曖昧だと志望動機全体の説得力が失われてしまいます。
明確な動機を見つけるためには、システムの土台を支える技術への興味や、安定性・可用性への責任感、技術の進歩への対応といった観点から自分の価値観を振り返ってみましょう。
例えば、過去に「縁の下の力持ち」的な役割で喜びを感じた経験や、問題解決やトラブルシューティングに興味を持った場面があれば、それをインフラエンジニアの仕事と結び付けることができます。
また、自分の価値観や興味をインフラエンジニアの業務内容と照らし合わせて共通点を見つけ、具体的なエピソードと組み合わせて表現することも重要です。
入社後にどのようなキャリアビジョンを描いているのかを書く
入社後にどのようなインフラエンジニアになりたいと思い、どのような仕事をしたいと考えているのか、しっかりと将来設計を持っていることを示すことも大切です。
そうすることで、インフラエンジニアとして働きたいという意欲や熱意を伝えることができるはずです。
特に同業他社からの転職の場合は、即戦力として期待されているため、ここがしっかりしていないと印象が悪くなってしまうので注意しましょう。
キャリアビジョンは短期・中期・長期に分けて考え、短期目標では基礎技術の習得や資格取得、中期目標では専門領域の確立やプロジェクトリーダー、長期目標では技術スペシャリストやマネジメントといった段階的な成長を描きます。
また、クラウドアーキテクトやセキュリティエンジニア、SREなど具体的な技術領域を示したり、インフラ自動化や災害対策、コスト最適化など貢献したい分野を明確にしたりすることも効果的です。
インフラエンジニアの志望動機で使える例文
続いては志望動機の例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
未経験者の場合
未経験者の志望動機は、学習意欲・適性・転職理由の3要素を効果的に組み合わせ、将来の成長可能性を具体的に示すことが重要です。
未経験者は実務経験で差別化できないため、ポテンシャルと熱意で勝負する必要があり、採用担当者は「この人は本当にインフラエンジニアとして成長できるか」「すぐに辞めないか」「基礎的な適性があるか」を重点的に評価します。
【例文】
貴社の充実した社員教育プログラムに惹かれ志望しました。
私はこれまで総務で働いていましたが、ある時知人からインフラエンジニア職についての話を聞く機会がありました。
そのお話の中で、自分が普段意識していないだけで、実は私たちの快適な生活はインフラエンジニアの方々の活躍の上に成り立っているのだと気づかされ、感銘を受けました。
次第に自分もインフラエンジニアの一員となりたいと願うようになり、今ではCCNAの資格取得を目指して独学で勉強を行っています。
ITインフラに関わる仕事は未経験ですが、前職で培ったコミュニケーションスキルやスケジュール管理能力などを活かし、一刻も早く会社に貢献できることを目指したいと思っています。
経験者の場合
経験者の志望動機は、これまでの技術経験と実績を具体的に示し、転職理由とキャリアアップの方向性を明確にして、応募企業でしか実現できない成長ビジョンを提示することが重要です。
経験者は実務経験があるため、未経験者とは異なり「即戦力性」と「さらなる成長可能性」の両方が評価され、採用担当者は「どのような技術スキルがあるか」「なぜ転職するのか」「この企業でどのような価値を提供できるか」を重点的に評価します。
これまでの経験を整理し、応募企業の事業内容や技術方向性と照らし合わせて、最も関連性の高いスキルと経験を重点的にアピールし、転職理由は前向きで具体的な成長意欲として表現することが大切です。
【例文】
私が貴社を志望した理由は上流工程の実績が魅力的だったからです。
前職では3年間にわたりLinux系のハードウェアやミドルウェアなどの構築業務に携わってきました。
しかし、今後は構築業務だけでなく設計業務にも携わることのできるインフラエンジニアへステップアップしたいと考えています。
前職で経験してきた構築ノウハウを活かし、即戦力として貴社に貢献できることを望んでいます。
新卒者の場合
経験の有無にかかわらず、就職活動において「なぜインフラエンジニアになりたいのか」「なぜその会社を選んだのか」をはっきりと具体的に示すことは必要不可欠です。
当たり前ですが、新卒の場合、社会人経験がないうえに実務経験がありません。
そのため、一見アピールできることが少なく思われますが、関連する資格を取得したり英語力を身につけたりと、いかに実務に直結するような能力があることをアピールするかが重要です。
【例文】
私は、情報社会の基盤を支えるインフラエンジニアとして、安定したシステムの構築と運用に携わりたいと考えています。
大学で情報工学を専攻し、ネットワークやサーバーの基礎知識を学ぶ中で、システムの安定性やセキュリティの重要性に気づきました。
また、ネットワークスペシャリストやLPICなどの資格にも挑戦し、サーバーやネットワークの設計・運用に関する理解を深めてきました。
これらの資格を通じて、システムの安定性やセキュリティ向上に貢献できる技術力を養ってきました。
インフラは企業や社会の根幹を支える役割を果たしており、その一翼を担うことに大きなやりがいがあるのではないかと感じています。
貴社のインフラ整備や最新技術の導入に興味を持ち、自分の知識と技術を活かして、より安全で効率的なシステムの構築に貢献したいと考えています。
未経験ではありますが、積極的に学び続ける姿勢と、チームで協力して課題を解決する意欲には自信があります。
貴社でのインフラエンジニアとしてのキャリアを通じて、社会に役立つインフラの構築に携わりたいと強く願っています。
文系出身者の場合
文系出身者でもインフラエンジニアを目指す人は少なくありませんが、大学時代での学びをどうアピールすればいいかわからないという人は多いかもしれません。
「なぜ文系でありながらインフラエンジニアを目指すに至ったのか」「インフラエンジニアとは無関係の講義や授業が多い中でどのようなことを学んできたか」の2点は非常に重要視されるポイントであるため、インフラエンジニアを目指すうえで、いかにその逆境を乗り越えたか、いかに克服してきたかを具体的に説明するのがポイントです。
【例文】
私はこれまで人文科学を専攻し、主に社会や文化、コミュニケーションに関する知識を深めてきました。
しかし、大学時代にITやインターネットの発展に触れる機会が多く、その中で「技術を通じて社会に貢献したい」という思いが芽生えました。
なかでも、インフラエンジニアの仕事は、企業や社会の基盤を支える重要な役割を担っており、その安定性と社会的意義に魅力を感じています。
私の強みは、文系出身ならではのコミュニケーション能力や問題解決力です。
例えば、大学のゼミ活動やグループワークを通じて、多様な意見を調整しながら最適な解決策を導き出す経験を積んできました。
これらのスキルは、インフラの運用やトラブル対応においても、関係者と円滑に連携しながら課題を解決する上で大いに役立つと考えています。
また、私はITに関する自己学習も積極的に行っており、オンラインのプログラミング講座やネットワークの基礎知識を独学で習得しています。
具体的には、Linuxの基本操作やネットワークの仕組みについて学び、仮想環境を構築して実践的なスキルを身につけました。
これらの経験を通じて、技術的な知識の習得に対する意欲と粘り強さを養ってきました。
私は貴社の革新的な技術開発に魅力を感じて志望しました。特に、○○プロジェクトでの取り組みを知り、自分のスキルを活かして貢献したいと思ったからです。
また、御社の企業文化や社員の方々の熱意に共感し、長期的に成長できる環境だと感じました。
貴社のインフラエンジニアとして、未経験ながらも積極的に学び続け、チームの一員として貢献できるよう努力してまいります。
インフラエンジニアの志望動機でありがちな失敗例と注意点
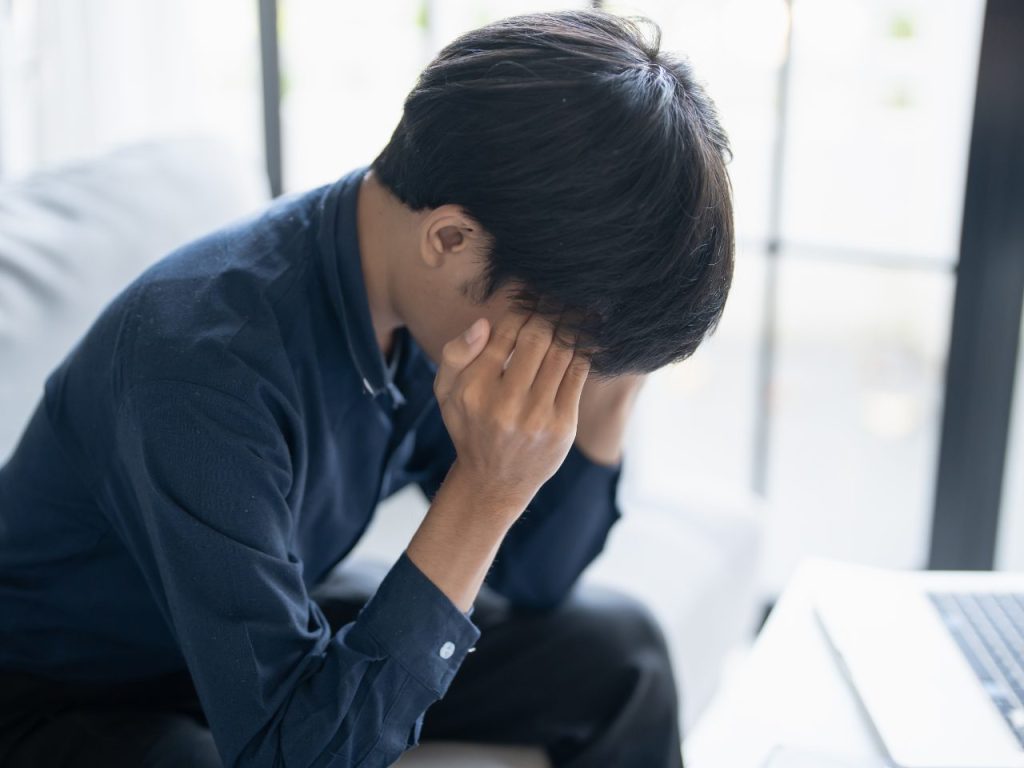
インフラエンジニアの志望動機でありがちな失敗例としては、主に以下のようなものが挙げられますが、ここからはそれぞれの失敗例について具体的に解説しながら志望動機を書く際の注意点について解説していきます。
- テンプレート感が強く、特別な思い入れや熱意が感じられない
- 前職への不満が目立ち、全体的にネガティブな内容となっている
- 学習意欲が伝わりにくい受け身な内容で、入社後の成長がイメージしにくい
- 給与や待遇、福利厚生、教育体制が志望動機のメインとなっている
- 将来的な独立を示唆する内容で、企業への貢献度が低いと見なされる
テンプレート感が強く、特別な思い入れや熱意が感じられない
テンプレート感の強い志望動機は、採用担当者に「本気度が低い」「企業研究が不足している」という印象を与え、選考で不利になる最も避けるべき失敗例です。
採用担当者は多数の志望動機を読むため、どの企業でも使い回せる内容はすぐに見抜かれてしまいます。
テンプレート的な志望動機は、その企業への特別な思い入れや具体的な志望理由が感じられないため、「他の企業が第一志望で、ここは滑り止め」という印象を与えてしまう危険性があります。
具体的な失敗例としては、「ITの発展に貢献したい」「技術力を向上させたい」「成長したい」といった抽象的な表現の多用や、「御社の理念に共感しました」「御社で成長したいです」といった企業名を入れ替えるだけの内容が挙げられます。
テンプレート感を避けるためには、企業の具体的な事業内容、技術領域、企業文化を詳しく調べ、その企業ならではの特徴と自分の経験や目標との関連性を明確に示すことが重要です。
企業のWebサイト、ニュースリリース、社員インタビューなどから独自の情報を収集し、オリジナリティのある志望動機を作成することが成功の鍵となります。
前職への不満が目立ち、全体的にネガティブな内容となっている
前職への不満を強調する志望動機は、採用担当者にネガティブな印象を与え、「同じ理由で当社も辞めるのではないか」という懸念を抱かせる危険な失敗パターンです。
転職理由として前職への不満を述べることは理解できますが、それを志望動機の中心に据えることは逆効果になります。
採用担当者は「問題解決能力の欠如」「協調性の欠如」「責任転嫁の傾向」を疑う可能性があり、ネガティブな内容が多い人材は職場の雰囲気を悪化させるリスクがあると判断され、採用を避けられる傾向があります。
具体的な失敗例としては、「前の会社は給料が安く、残業も多かったので転職を決意しました」といった待遇への不満や、「職場の人間関係が悪く、上司とも合わなかったため」といった人間関係の問題を前面に出す表現が挙げられます。
前職への不満は転職理由として面接で聞かれた際に簡潔に述べるに留め、志望動機では前向きな理由を中心に構成することが重要です。
「新しい技術への挑戦」「より大きな責任を担いたい」「専門性を深めたい」など、成長志向の表現に置き換えることで、ポジティブな印象を与えることができます。
学習意欲がわりにくい受け身な内容で、入社後の成長がイメージしにくい
学習意欲が伝わらない、かつ受け身な志望動機は、技術の進歩が早いIT業界において「継続的な成長が期待できない」という判断を下され、特に未経験者にとって致命的な失敗要因となります。
具体的な失敗例としては、「御社で技術を教えていただきたい」「研修制度が充実しているので安心です」といった受け身な表現や、「安定した環境で働きたい」「これまでの経験を活かしたい」といった現状維持志向の内容が挙げられます。
一見勤勉性を示せるのでプラス評価になるように思えるかもしれませんが、志望動機としては適切とはいえません。会社は学ばせていただく場所ではなく、「企業の利益に貢献する」場所だからです。
学習意欲を示すためには、現在取り組んでいる学習内容、取得済みまたは取得予定の資格、読んでいる技術書籍、参加している勉強会などを具体的に記載することが重要です。
また、入社後の学習計画や目指したい技術領域も明確に示すことで、継続的な成長意欲をアピールでき、数値や期限を含めた具体的な目標設定も効果的です。
給与や待遇、福利厚生、教育体制が志望動機のメインとなっている
給与などの待遇面や福利厚生は企業側にとってのアピール部分でもあるので、必ずしも理由にしてはいけないというわけではありません。
しかし、待遇面や福利厚生ばかりを全面に押し出すと、企業側からすれば「ウチより待遇がよければすぐにやめてしまうのだろうか」と不安に思われてしまいます。
また、教育制度への過度な依存を示す志望動機も、自立的な学習能力の欠如と受け身の姿勢を印象づけ、技術者として求められる自己成長力への疑問を抱かせる問題のある表現です。
教育制度への依存は「自分で学習する意欲がない」「会社任せの姿勢」という印象を与え、特に技術者としての成長可能性に疑問を持たれかねません。
そのため、「充実した研修制度があるので安心して入社できます」「新人教育プログラムが整っているため御社を志望しました」といった表現を避け、「御社の技術環境で自主的に学習し、実践的なスキルを身につけたい」「先輩方と協働しながら、自らも積極的に技術習得に取り組みたい」といった主体的な学習姿勢を示す表現に置き換えることが重要です。
教育制度への言及は最小限に留め、自主的な学習計画や既に取り組んでいる勉強内容を中心にアピールしましょう。
将来的な独立や起業を示唆しており、企業への貢献度が低いと見なされる
規模を問わず、ほとんどの企業が長期で会社に貢献してくれる人を採用し、成長させたいと思っており、そのために教育制度を充実させたり、快適な職場環境を整えたりしています。
そのような状況のなかで、志望動機から将来的な独立・企業のためにスキルを身につけたいというようなことが窺えれば、マイナス評価につながってしまう可能性があります。
経営者を育てたり、起業を促したりするような社風の企業であれば問題ないかもしれませんが、スキルをある程度身につけたら退職してしまう人を社内で積極的に採用しようと思う企業は稀であるため、仮に独立の意思があったとしても志望動機には書かない方が無難です。
インフラエンジニアの採用面接での志望動機の伝え方

この章では、面接において志望動機を効果的に伝えるための重要なポイントについて紹介します。面接での志望動機の伝え方には主に以下の内容があります。
- 面接官からの深掘り質問に対する事前準備と回答戦略
- 説得力を高める具体的なエピソードの選定と構成方法
- その企業を選んだ明確な理由の整理と効果的な伝え方
深掘り質問への準備
面接での深掘り質問への準備は、志望動機の真の理解度と本気度を示すために不可欠であり、表面的な回答では通過できない選考の重要な関門です。
面接官は志望動機を聞いた後、必ずと言っていいほど深掘り質問を行います。
これは応募者の本気度、論理的思考力、企業理解度を測るためで、表面的な準備しかしていない場合、深掘り質問で矛盾が生じたり、答えられなかったりして、志望動機全体の信憑性が疑われます。
「なぜインフラエンジニアなのか?」に対して「なぜ開発エンジニアではダメなのか?」といったより詳細な質問や、「技術に興味がある」に対して「具体的にどの技術領域に興味があるのか?」「その技術を学ぶために何をしているか?」といった実行力を問う質問が予想されます。
志望動機の各要素について「なぜ?」を5回繰り返し、根本的な理由まで掘り下げて準備することが重要で、想定される質問をリストアップし、それぞれに対する具体的で一貫性のある回答を用意し、矛盾のない論理的なストーリーを構築することが大切です。
具体的なエピソードの準備
具体的なエピソードの準備は、志望動機に説得力と信憑性を与える最も効果的な手法であり、面接官の記憶に残る印象的な回答を作り出すために必要不可欠です。
抽象的な説明だけでは面接官に強い印象を与えることができないため、具体的なエピソードは応募者の人柄、価値観、行動パターンを示すとともに、志望動機の根拠を裏付ける証拠としての役割を果たします。
ストーリー形式で語ることで面接官の関心を引きつけ、記憶に残りやすくなる効果もあります。
例えば、「大学時代にサーバーがダウンしてゼミの発表ができなかった経験から、インフラの重要性を実感しました」といった技術への興味のきっかけや、「資格取得のために毎朝1時間早起きして3ヶ月間継続し、合格を達成しました」といった学習への取り組みなど、具体的な状況と行動を示すエピソードが効果的ですね。
STAR法を使ってエピソードを構成し、状況→課題→行動→結果の流れで整理し、数値や具体的な成果があれば必ず含め、そのエピソードから何を学んだか、どう成長したかも明確に説明することが重要です。
企業志望理由の明確化
企業志望理由の明確化は、数ある選択肢の中からその企業を選んだ特別な理由を示し、採用担当者に「この人は本気で当社に入りたがっている」という確信を与えるために最も重要な要素です。
面接官が最も知りたいのは「なぜ他社ではなく当社なのか」という点で、曖昧な企業志望理由は「どこでもいいのではないか」「第一志望ではないのではないか」という疑念を抱かせてしまいます。
明確で具体的な企業志望理由は、企業研究の深さと入社への本気度を示し、採用後の定着率や活躍への期待を高める効果があります。
「御社の医療システム事業において、人命に関わるシステムの安定稼働を支えたい」といった事業内容への共感や、「御社が先進的に取り組んでいるクラウドネイティブ技術を学び、実践したい」といった技術領域への関心を示すことが効果的です。
企業の公式情報だけでなく、技術ブログ、社員インタビュー、業界ニュースなどから独自の情報を収集し、その企業ならではの特徴を複数見つけ、競合他社との違いも明確にして、なぜその企業でなければならないのかを論理的に説明できるよう準備することが重要です。
インフラエンジニアの志望動機についてよくある質問
インフラエンジニアでの志望動機ではどのよう点が評価される?
インフラエンジニアの志望動機で評価されやすいポイントとしては、主に以下のようなことが挙げられます。
- 具体的なスキルや経験を効果的にアピールする自己PR要素
- 企業への強い入社意欲と本気度が伝わる熱意の表現
- 継続的な学習姿勢と責任感を示す勤勉性のアピール
- 企業の事業や技術領域との明確な関連性と理解度の表示
フリーターからインフラエンジニアを目指す際の志望動機の書き方は?
フリーターからインフラエンジニアを目指す場合は、これまでのアルバイト経験で培ってきたスキルや自分の得意分野・強みをアピールすることが重要です。
ただし、ただ単に自分の強みをアピールするだけでは具体性や説得力に欠けてしまうため、自分の得意分野や長所のなかからインフラエンジニアと関連性のありそうなものを見つけ、それを企業でどのように活かしていきたいかを語るようにしましょう。
未経験を積極的に採用している企業であれば、応募者の人柄や将来性を重視する傾向があるため、これまでの経験や得意分野、好きなことを自分の言葉で伝えるようにすることが最も大切です。
志望動機を書くときにアピールポイントが少ない場合は?
インフラエンジニアを志望している方のなかには、自己PRやアピールポイントに書けることが少ないとお悩みの方も多いかもしれません。そのような方は、以下のようなポイントに注目して自分に当てはまっていないかチェックしてみると良いでしょう。
- パソコンを触るのが好き、長時間触るのも平気
- 客観的な目線を持ち、常に冷静な判断ができる
- コミュニケーション力が高く、協調性がある
- コツコツと細かな作業を続けられる
自分のアピールポイントが少ない場合は、以上のようにインフラエンジニアとはどのような職業であるのかを分析し、どのような人が向いていそうかを想像してみるのがコツです。
まとめ
今回はインフラエンジニアの志望動機に関するお役立ち情報をご紹介しました。
インフラエンジニアはITインフラの設計や構築、運用、保守などを担うエンジニアです。専門的な職種なので、志望動機にも専門性が求められます。勉強している内容や、取得を目指している資格名などを交えて記述するとよいでしょう。
また、なぜインフラエンジニアという職種を選んだのか、そしてなぜその企業で働きたいのかについて、明確な理由を考えておくことが大切です。
\ 転職後の就業継続率97%の転職支援 /
関連記事
インフラエンジニア
- インフラエンジニアの平均年収は? 1000万円を達成する方法も紹介
- インフラエンジニアの将来性とは?今後の需要予測についても解説
- 【最新版】インフラエンジニアにおすすめの転職エージェント5選|転職成功のコツやおすすめの資格を徹底解説





