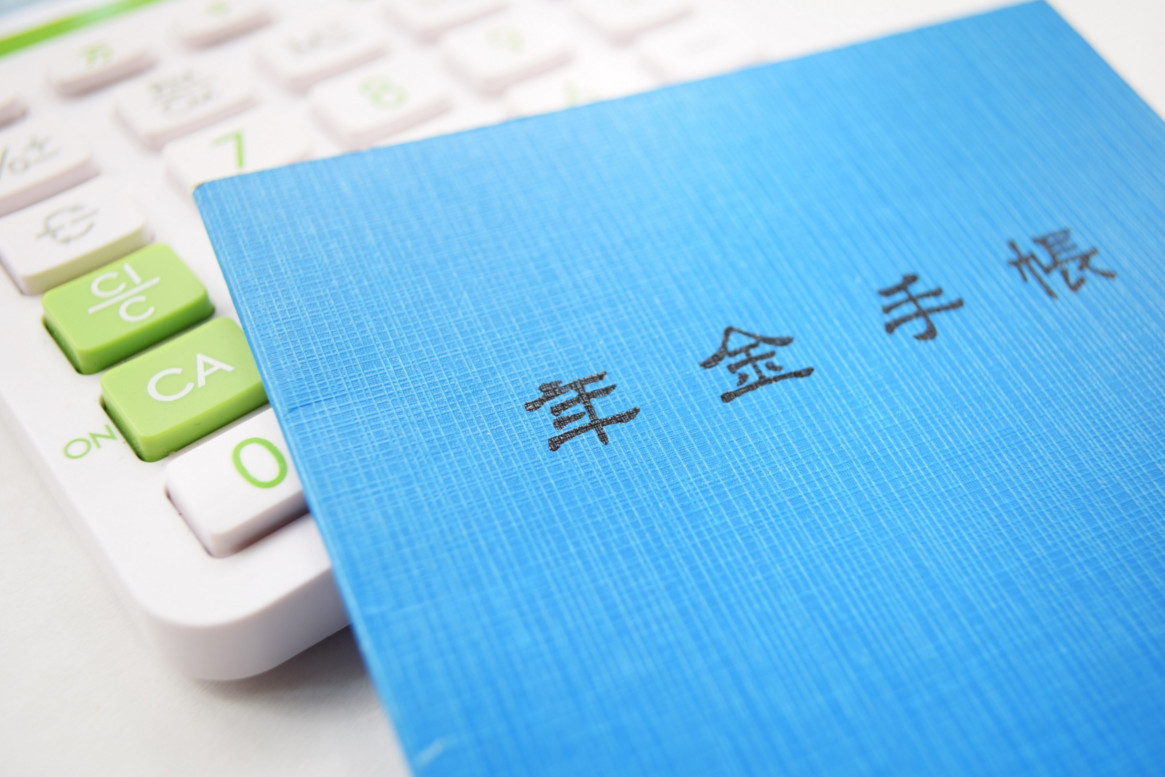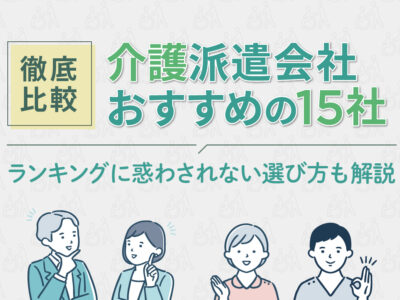いざ離婚をしようと婚姻中に話し合いを進めていると、お金や物品などの財産分与や離婚手続き、こどもがいる場合は親権や養育費などの話が出てきます。
そのなかでも、忘れられがちなのは年金や保険などの変更手続きです。
離婚となると、パートナーの扶養から外れるのでそれまでの保険や年金は改めて手続きをしないと後に保険が使えないなどのトラブルになってしまいます。
ですが、年金や保険などの手続きはどうしたら良いのか、よくわからない方もいます。
ここでは、離婚をする際の年金や保険の変更手続きや、保険料を支払えないときはどうすれば良いかなどを解説していきます。
これから離婚を検討している方は、手続きを忘れないよう参考にしてくださいね。
- 離婚後に仕事はある?派遣社員ならブランクがあってもできる仕事を紹介!
- 離婚前までは専業主婦をしていた方は、離婚をしたら生活するために働かなくてはなりません。とくに、健康保険(社会保険)に加入したい方は、条件を満たした働き方を選ぶ必要があります。
派遣会社なら、仕事ができるか不安な方でも、ブランクがあってもできる仕事を紹介しています。まずは登録をしていただき、どうすれば加入条件を満たして働けるか担当者にご相談ください。
ウィルオブへの登録はこちら
目次
離婚をしたら保険や年金はどうなる?
戸籍上で離婚が成立したら婚姻関係は解消ですが、同時に「扶養家族」という関係性も成立しなくなります。
そのため、パートナーの医療保険に関する保険資格は、離婚成立と同じタイミングで喪失してしまうのです。
そのため、保険についての手続きは別途自分自身で行わなければなりません。
公的医療保険の種類と変更手続き
日本には国民皆保険制度があり、国民全員が公的医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入しなければいけません。
多くの場合、婚姻期間中に世帯主となるパートナーの公的医療保険に加入し、それを利用しています。
そのため、離婚をしてしまうと他人となるのでこの医療保険はそのままの形で引き続き利用することはできないのです。
ここでは、健康保険(社会保険)と国民健康保険によってどのような手続きを行うのかを説明していきます。
健康保険(社会保険)
パートナーの扶養家族として健康保険に加入していた場合は、健康保険に加入していた家族がいなくなると資格を失ってしまいます。
そのため、健康保険に加入し続けたい場合は変更手続きを行い、今度は自分の名義で加入するか、親などの家族の扶養に入るようにしましょう。
パートナーの扶養から外れる手続きを行う際、「資格喪失証明書」が必要となるので加入者の勤務先に書類の依頼をしてください。
【新たに健康保険に加入する場合】
健康保険は、会社に所属している方が加入できるものなので、正社員や条件に合う働き方をしていれば加入できるものです。
そのため、パートナーの扶養家族から外れた際は、勤務先に資格喪失証明書を提出し、自分名義で健康保険に加入する手続きをしてもらいます。
【親の扶養家族として加入する場合】
親が会社勤めをしていれば、その扶養家族や世帯の一員になることで健康保険に切り替えることができます。
健康保険に加入している親の勤務先に資格喪失証明書を提出してもらい、手続きをしてもらいます。
ですが、親が自営業の場合は加入している保険は国民健康保険なので、扶養家族としての加入はできません。
国民健康保険には扶養という制度がないため、自分を世帯主として加入手続きを行ってください。
【健康保険から外れる場合】
なかには、健康保険の加入条件に当てはまらない働き方をするため、健康保険から外れる場合もあります。
地区町村の役場に資格喪失証明書を提出し、自分名義の国民健康保険に切り替える手続きを行いましょう。
【離婚前から自分名義の健康保険に加入していた場合】
婚姻の時から、自分名義で健康保険に加入していた方もいます。
離婚によって姓が変わることもあるため、必要に応じて名義変更の手続きを行う必要があります。
また、パートナーが自分名義の健康保険に入っていた場合は、パートナーを扶養から外すために勤めている会社に資格喪失証明書の作成を依頼してパートナーに渡してください。
この書類がないと、扶養から外れるパートナーは新たな保険に加入することができないので、保険資格を失ってから5日以内に手続きを行いましょう。
子どもも扶養から外れるのであれば、子どもの分の手続きも忘れないでくださいね。
国民健康保険
国民健康保険は、健康保険(社会保険)への加入条件を満たしていない方や自営業・フリーランスなどをしている方などが対処となる保険です。
パートナーを世帯主として加入していた場合は、名義を自分のものに変更する必要があります。
この手続きには「国民健康保険被保険者資格喪失届」が必要となることもあるので、必要に応じて用意をしておきましょう。
【自分を世帯主として加入する場合】
離婚後に働く場合は、健康保険(社会保険)の加入条件を満たしていれば会社を通して自分を世帯種として加入手続きを行い、完了したら国民健康保険を抜ける手続きをします。
健康保険の加入条件を満たしていない場合は、市区町村の役場で自分名義の国民健康保険への加入手続きをしてください。
国民健康保険は働いている・働いていない関係なく国民健康保険に加入しなくてはなりません。
離婚後、働く予定がない方も自分を世帯主としての名義変更の手続きを市区町村の役場で行う必要があります。
【パートナーを世帯主として加入していた場合】
世帯主であったパートナーに国民健康保険被保険者資格喪失届を市区町村の役場に提出してもらい、パートナーの世帯から外れることができます。
その後、自分を世帯主とした国民健康保険への加入手続きを行いましょう。
また、親が健康保険(社会保険)に加入している場合は、国民健康保険ではなく扶養家族として健康保険に加入することができますよ。
子どもがいる場合
子どもがいる場合も、パートナーの加入・脱退・変更手続きと同じなので同時に行うことができます。
離婚の話し合いをする際、どちらが子どもの世帯となるかについても話しておくことで、子どもも保険に関する手続きが必要かを確認しておいてください。
自分が世帯主として保険への加入・変更手続きを行う際も子どもの手続きを忘れないようにしましょう。
保険手続きの注意点
ここからは、離婚をして健康保険(社会保険)や国民健康保険の加入・変更手続きを行う際の注意点を紹介します。
手続きに必要な日数などがありますので、事前に確認をして不備が内容にしてください。
保険の手続きはなるべく早めに始める
離婚後、国民健康保険へ加入する場合は、原則として離婚してから14日以内に手続きを行わなくてはなりません。
ただ、世帯主であったパートナーに資格喪失証明書の作成依頼をしてもらったりするので、手続きが思うようにいかないこともあります。
そうなった場合、保険に加入していない期間は無保険となるので、その間に診察を受けた分は全額自己負担となってしまいます。
ですが、この自己負担した分は、保険手続きが完了した後に市区町村の役場で還付金申請を行うことで、負担をした7割が戻ってきます。
こうした手間をなくし、安心して診察を受けられるように離婚前から保険手続きの話をしておきましょう。
資格喪失証明書は早くに取得しておく
資格喪失証明書は、世帯主となっていたパートナーが会社に作成依頼をすることで発行されます。
ですが、人によっては職場に離婚したことを言いづらかったり、意図して伝えてなかったりすることもあるため、手続きがスムーズにいかないこともあります。
会社は扶養から外れるなどの変更があったと申請されたら5日以内に書類を作成する必要があるため、遅い場合には催促するようにしましょう。
自分から催促しづらい場合は、家族や知人などの第三者に連絡をしてもらったり、市区町村の役場に相談をして問題を解決するようにしてください。
保険料の支払いが難しい場合は?
離婚後、これから仕事探しもこれからなどという状況では、健康保険料をきちんと支払えるのかどうかという不安もあるかと思います。
そこでまず、便利な計算アプリやサイトなどを使って、離婚後に支払わなければならない健康保険料を把握することから始めます。
保険料の職場負担があるとき/ないとき
離婚後に勤めることになった職場が保険組合を持つ会社等であれば、国民健康保険に入る必要はなく、健康保険料の半分を会社が負担してくれます。
たとえば、保険料が3万円なら、1万5千円を会社が負担してくれるので、実費は1万5千円の支払いだけでよいということになります。
しかし、即座にそのような職場に就職できない場合には、ひとまず国民健康保険に加入しなければいけません。
その時、どうしても国民健康保険の支払いが難しいようであれば、市区町村の役場に行って免除の申請をするという方法があります。
保険料免除申請の種類
市区町村の役場で担当課に行き、免除の申請を行います。
前年度の所得に応じて、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれに該当するかが決まります。
ただし、どの免除に該当するか、また申請自体が通るかどうかは、申請をしてみなければわかりません。
また、一度免除の申請が通ったとしても、期間限定の免除なので注意が必要です。
国民年金の変更手続き方法

公的医療保険同様、国民年金に関しても自分自身で変更手続きを取らなければいけません。
自分がどの被保険者区分に該当するかを確認し、それぞれに応じた手続きを取ります。
【被保険者の区分】
| 第1号被保険者 | 自営業や学生など、国民年金保険料を自分で納めている |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入し、国民年金保険料が給与から引かれている |
| 第3号被保険者 | 厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、届出を出し手続きを取ることで国民年金保険料を負担する必要がない |
婚姻中「第1号被保険者」だった場合
とくに変更手続きを必要としない場合が多いのですが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方の場合、市役所等に変更届を提出する必要があります。
婚姻中「第2号被保険者」だった場合
勤務先によって手続きが変わるので、くわしいことは勤務先に問い合わせてください。
婚姻中「第3号被保険者」だった場合
基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類、離婚成立日が確認できるもの(離婚が反映された戸籍謄本や離婚届受理証明書など)、扶養から外れた日が確認できるもの(被扶養者資格喪失証明証など)を持参の上、市町村役場の担当部署にて「第1号被保険者」への変更手続きを行います。
詳細は、居住自治体のホームページなどをご確認ください。
年金の支払いが難しい場合は?
保険料を未納のままにしておくと、将来「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取ることができなくなる場合があります。
収入の減少や失業等によって国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用します。
前年度所得が一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができ、健康保険料同様に全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除が決まります。
【国民年金保険料免除・納付猶予制度のメリット】
- 手続きをせずに「未納」となった場合、将来的な「老齢年金」受取り金額はゼロになってしまいますが、保険料を免除された期間に関しては年金額の2分の1を受け取ることができます。
- 保険料免除・納付猶予を受けている期間でも、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
もしも受給する年金額を増やしたい場合は、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。
年金分割制度とは?
離婚に関しては、「年金分割制度」を利用することができます。
これは平成19年に厚生年金法が改正された際に、設けられた制度です。
将来給付される年金の総額を分けるわけではなく、配偶者が納付した厚生年金保険料の一部を、自分が納めたことにするという仕組みです。
ここでは、2種類の年金分割制度とその手続きについて紹介します。
【合意分割】
- 婚姻期間中の厚生年金保険「納付記録」があること
- 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年)を経過していないこと
- 当事者双方の合意、または裁判手続きによって分割割合を定めていること
- ただし分割割合が、5割を超えてはいけない
- 所定の手続きを経て分割割合が決まり次第、年金事務所にて合意分割の請求手続き
【3号分割】
- 平成20年4月1日以後に、国民年金「第3号被保険者」期間を有すること
- 分割割合は5割とすること
- 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年)を経過していないこと
- 年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出するだけで、手続きは完了
とくに、専業主婦だった場合や、バイト・パートだった場合には、年金分割制度の活用をおすすめします。
ダブルインカムであれば、双方の収入を確認して年金分割を請求すべきか否かを決めます。
年金分割により分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金のみです。
よって、夫が自営業(個人事業主)だった場合は国民年金しか加入しておらず、妻が年金分割を請求することはできません。
婚姻期間が短い場合や、会社員だった夫が事業を始めたという場合は年金分割が少ない可能性があるのを覚えておきましょう。
また、注意点として忘れてはならないのが、年金分割をしたからと言って、すぐに年金を受け取れるわけではないということ。
自分自身が年金を受給できる年齢に達して初めて受け取れるのです。
そのため、たとえ夫が定年退職して年金を受給されていたとしても、妻がその年齢(原則65歳)にならなければ受け取れません。
年金受給年齢に達したときに後悔しないためにも、事前の準備をしっかり行っておきましょう。
40歳を過ぎて再就職したい人にはウィルオブがおすすめ
専業主婦だったが離婚をしたので再就職を目指す、会社との契約更新を断られて仕事を探しているという人におすすめしたいのが、人材会社「ウィルオブ」です。
ブランクを感じる人や、希望する仕事がなかなか見つからない人を就職するまでサポートしています。
未経験でも活躍できる仕事もたくさんあるので、新たな気持ちで就職先を見つけることができますよ。
まとめ
離婚を考えている方で、離婚後の保険の手続きについて話をしてきました。
保険の名義や加入変更などは、離婚をして自動的に切り替わるものではないので、自分で手続きを行ってください。
加入変更をしないと場合によっては無保険の期間ができてしまうので、その期間は申請すれば7割戻るとしてもその時は全額支払わなくてはならないのです。
また、子どもがいる家庭であれば、子どもの保険の変更手続きも夫婦の手続きと一緒に行えるので、忘れないようにしましょう。
そして、手続きに必要な書類の資格喪失証明書の発行は、世帯主が勤めている会社に依頼するので、トラブルが起こる可能性もあります。
トラブルが起こってしまうと、その分変更手続きも遅れてしまうため、早めの行動を心がけましょう。
今回の記事でも説明をしていますが、くわしい手続きについては各市区町村の担当課に問い合わせて不備が内容手続きを進めてください。
- 保険や年金加入の条件を満たして働きたい方は派遣会社にご相談ください
- 保険や年金の手続きが完了しましたら、その状況を維持するためには仕事を見付けることが大切です。ですが、ブランクがあったり、経験自体がない方は一人で仕事を見つけるのは一苦労です。
そこで、派遣会社に登録・相談をすることで、より早くあなたに合う仕事を見付けられる可能性が高くなります。再就職で悩まれている方は是非一度ご相談ください。
まずはこちらから登録を